COLUMNコラム
【2024年改定】コアウェブバイタルとは? SEOでの影響力や指標の変更点を解説
コアウェブバイタルは、Webサイトのユーザー体験を数値化するためにGoogleが導入した指標です。2021年6月に導入された比較的新しい指標で「読み込み速度」「インタラクティブ性」「視覚的安定性」の3つを評価し、ユーザー体験の快適さ(UX)を測ります。
Web担当者の中にはこの指標がSEOにどの程度の影響力を持っているか気になっている方も多いのではないでしょうか? そこで、記事では、SEOにおける役割や優先度、2024年に改定された指標について解説します。また、基本的改善方法についても取り上げます。
これからSEO対策としてコアウェブバイタルの改善を実施すべきか迷っている方、実施を検討している方は、ぜひ記事をご参照ください。
コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは?
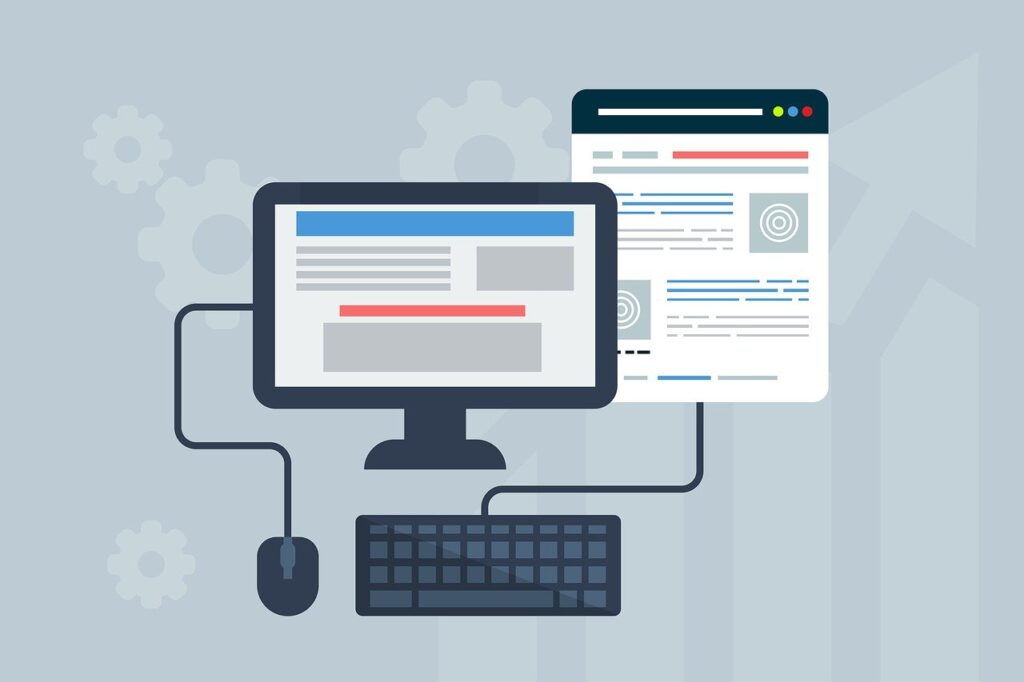
コアウェブバイタルはUXを測る主要な指標の1つです。
UXとは「User eXperience(ユーザーエクスペリエンス)」の略で、ユーザーがサービスや製品を利用して得られる「使いやすさ」「快適さ」などの体験を示す言葉で、日本語では、ユーザー体験と訳されます。
ここでは、コアウェブバイタルのSEOにおける役割や優先度、実施の目安について解説します。
SEOでの役割はユーザー体験の向上
SEOにおいて、コアウェブバイタルは、ユーザー体験を向上させるための指標として活用されます。
Webサイトのユーザー体験を高めると、SEOランキングにも良い影響が期待できるようになります。ユーザー体験の向上は、訪問ユーザーの滞在時間やクリック率の増加といった、検索エンジンが評価するポジティブなユーザー行動を促進するからです。
コアウェブバイタルは、Webサイトの読み込み速度、視覚的安定性、インタラクティブ性を得点化する指標です。数値を確認することで、Webサイトのユーザー体験を客観的に評価し、具体的な改善点を特定することが可能になります。
コアウェブバイタルはSEOにおけるユーザー体験を評価するパフォーマンス指標としての役割があります。
SEOの「補助的」なランキング要因
では、コアウェブバイタルの数値はSEOにどの程度影響を与えるのでしょうか? 結論から申し上げますと、コアウェブバイタルは、水準以上に高めても良い影響を見込めません。その一方で、水準を満たさないと無視できない悪影響を及ぼします。
GoogleのWebマスタートレンドアナリストであるジョン・ミューラー氏は、Linkedlnでコアウェブバイタルについて発言しています。要約すると次の通りです。
「コアウェブバイタルの数値をSEOのために微調整するのは非効率的だ。満点を取るのは技術的なチャレンジにはなるが、サイトのランキングに大きく影響しない」
コアウェブバイタルは「補助的」なランキング要因です。これは「競合相手が同ジャンル同品質のページ」といった限定的な場面であれば、高い方が上位になる、くらいの認識でいいと思います。よって、水準以上にコアウェブバイタルを高めることは、SEOを達成する上で効率的ではありません。
一方で、コアウェブバイタルの水準を満たすことは重要です。たとえば、GoogleはWebページの読み込み時間が長ければ長いほど、モバイルユーザーの離脱率が上昇する、という報告を出しています。この中では、読み込み時間が1〜3秒の場合は32%、1〜5秒の場合は90%離脱率が高まる、というデータが提示されています。これは、ランキング争いにおいて無視できない悪影響です。
コアウェブバイタルは、水準以上に上げても大したSEO効果は見込めません。しかし、ランキング競争のスタートラインに立つためには水準を満たす必要があります。
SEOで改善を検討する目安
コアウェブバイタルが補助的なランキング要因でありながら、軽視できない指標だということが分かりました。
では、コアウェブバイタルは、どのようなタイミングで改善するのでしょうか?
大まかな目安としては以下の通りです。
①上位表示させたいページに「不良」判定が存在する場合
②サイト内の半分以上のページに「不良」判定が存在する場合
③実際にページにアクセスしてみて遅いと感じた場合
①②は後述するPageSpeed Insightsなどのツールで判定が可能です。
③はユーザー視点での体感速度が改善の目安になります。制作側が実際にアクセスして調査しましょう。とくにモバイル通信や低スペックデバイスでの遅延がないかは重要です。
コアウェブバイタルを構成する3つの指標
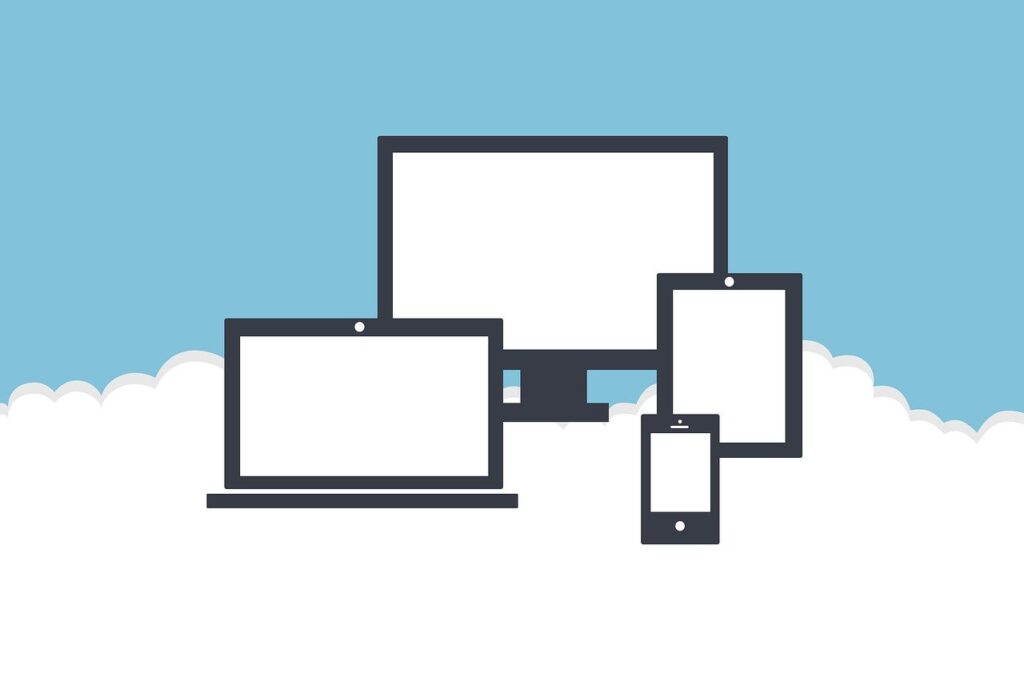
コアウェブバイタルがSEOに及ぼす影響力や、大まかな改善の目安が分かりました。
冒頭で述べた通り、コアウェブバイタルは以下の3つの指標によって構成されます。
「LCP」(Largest Contentful Paint ):読み込み速度
「CLS」(Cumulative Layout Shift):視覚的安定性
「INP」(Interaction to Next Paint):インタラクティブ性
ここでは、各指標の測定対象や具体的な推奨値などについて解説します。
「LCP」(Largest Contentful Paint ):読み込み速度
LCPは「ページの表示速度」や「読み込み時間」に対する評価指標です。ユーザーがページ内の最重要コンテンツをどれだけ早く見ることができるかを表しています。
測定対象はページの最大コンテンツが表示されるまでの時間(秒)です。
小さいほど評価が高く、Googleは2.5秒以内のLCPスコアを推奨しています。
LCPが小さくなるほどユーザーが素早く情報を得られるため離脱率が低下し、結果として快適なユーザー体験が提供されます。
「CLS」(Cumulative Layout Shift):視覚的安定性
CLSは、「視覚的安定性」に対する評価指標です。ユーザーが予期しないレイアウトのズレによって感じる不快な体験を表しています。
測定対象は、ページ読み込み中に発生する予期せぬレイアウトの移動です。分かりやすい例としては、ページ読み込み中に突然広告が表示され反射的にクリックしてしまった、などのユーザーが意図していないサイト内の行動です。
小さいほど評価が高く、Googleは0.1以下のCLSスコアを推奨しています。
CLSスコアが小さいほどユーザーの操作ミスを防ぎ、快適なユーザー体験を提供できます。
2024改定「INP」(Interaction to Next Paint):インタラクティブ性
INPは、「インタラクティブ性(応答性)」に対する評価指標です。ユーザーの操作に対してWebサイトのページやアプリが、どれだけ迅速かつスムーズに応答できるかを表しています。2024年3月に「FID」に代わってコアウェブバイタルの新しい指標として採用されました。
測定対象は、ユーザーの操作に対するページの反応速度(ミリ秒)です。たとえば、サイト内のボタンをクリックした際に、ページがどれだけ速く反応して処理を開始するかなどを測定します。
小さいほど評価が高く、Googleは200ミリ秒以下のINPスコアを推奨しています
INPスコアが小さいほどスムーズにページ情報を伝えられ、快適なユーザー体験を提供できます。
「FID」が「INP」に変更されてインタラクティブ性が精密化
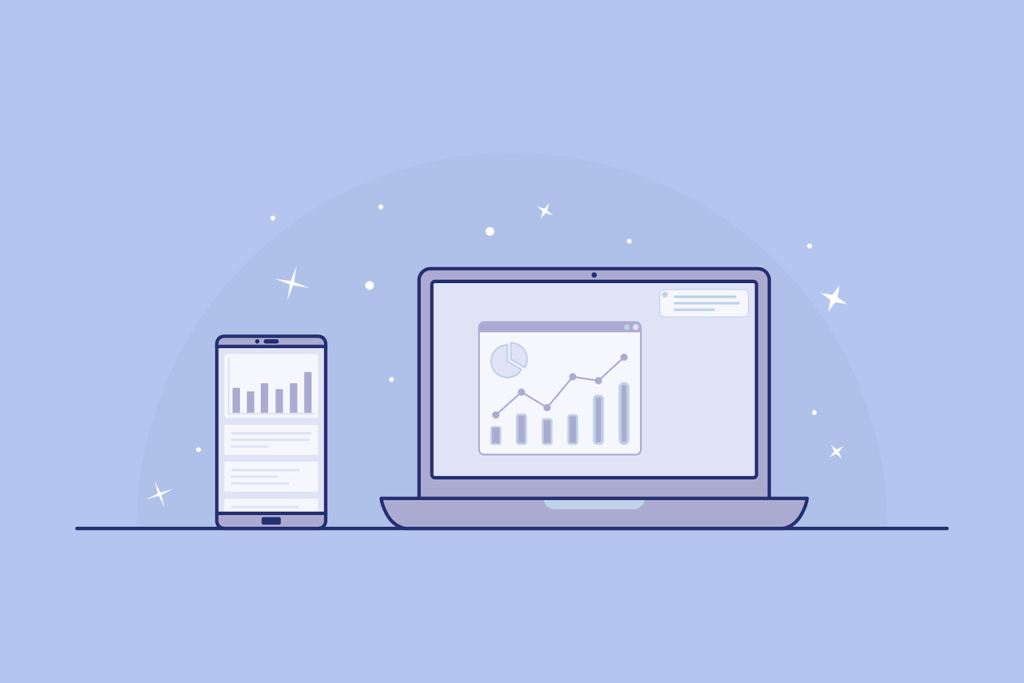
FIDがINPに変更されて、何が変わったのでしょうか?
FID(First Input Delay)は、INPと同じくインタラクティブ性に対する評価指標です。
しかし、FIDはユーザーがページで最初に操作を試みた時から、その操作に対する応答が始まるまでの遅延時間を測る指標です。測定範囲が狭く、INPと比較して、精密ではありません。以下は、FIDとINPの違いを簡単にまとめた表です。
| 項目 | FID | INP |
| 評価対象 | 初回入力の遅延時間 | 全ユーザー操作の応答速度 |
| 測定内容 | 最初の操作で処理が開始されるまでの時間 | 操作後、視覚的な変化が起こるまでの時間 |
| 対象操作 | ページ読み込み後の最初の操作のみ | ページ滞在中のすべての操作 |
大きな違いは、FIDが最初の操作のみを対象にしているのに対して、INPはページが表示されている間に発生するすべてのユーザー操作を対象にしていることです。
FIDが廃止されてINPが新指標になることで測定範囲が拡大し、コアウェブバイタルのインタラクティブ性は、より精密化しました。
コアウェブバイタルの測定方法
ここまで、コアウェブバイタルを構成する指標について解説してきました。では、これらの指標はどのように測定すればいいのでしょうか? ここでは、ツールを使用したコアウェブバイタルの測定方法について解説します。

PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)」
ページスピードインサイトは、Googleが提供しているWebパフォーマンスを測定できる無料ツールです。
Webページの表示スピードをコアウェブバイタル(LCP・CLS・INP)や他の重要指標で採点し、100点満点で数値化します。採点は90以上が「速い」、50-89が「平均」、49以下が「遅い」と判定されます。
使い方は以下の通りです。
①Webサイトにアクセスする
②計測したいWebサイトのURLを張り付ける
③分析を押して結果を待つ
ページスピードインサイトでは、URLを入力するだけで、データとテスト環境のスコアを簡単に確認できます。
Google Search Console(サーチコンソール)
Google Search Consoleは、サイトの検索順位を監視、管理、改善するのに役立つツールです。無料で利用できますが、Webサイト所有者向けのサービスなので、使用にはサイトの所有権を証明する必要があります。
機能の1つであるコアウェブバイタルレポートでは、サイト内のURLをLCP・CLS・INPで評価します。評価は「良好」「改善が必要」「不良」の3段階です。
コアウェブバイタルレポートは、サーチコンソール左側のサイドバーに「ウェブに関する主な指標」という項目をクリックすることで表示できます。
Google Search Consoleでは、自サイト全体のコアウェブバイタルに関する問題点を一覧でチェックできます。
Lifhthouse
Lighthouse(ライトハウス)は、Webページの品質を評価するためのChrome拡張機能です。Googleが開発し、無料で提供しています。
開発者向けに詳細な技術情報を提供するためのツールで、より技術的な視点から自分のWebサイトを分析します。評価項目は次の5つです。
Performance(パフォーマンス)
ページ読み込みや画像表示、ユーザー操作に対する反応の速さなどのWebサイトのパフォーマンスを評価する
Accessibility(アクセシビリティ)
障害者を含む全ユーザーや検索エンジンのクローラーにとって、サイトの情報や機能が利用しやすいかを評価する。
Best Practices(ベストプラクティス)
HTTPSを使用しているか、ブラウザにエラーコードがあるかなどのサイトのセキュリティ面を評価する。
SEO
メタディスクリプションの有無やrobots.txtは有効性など検索エンジンの最適化(SEO)がされているかを評価する
ProgressiveWebApp(プログレッシブウェブアプリ)
PWA(Webサイトのアプリ化)機能の実装状況を評価する
使い方は以下の通りです。
①アプリページを開きインストールする
②chrome拡張機能からLighthouseのアイコンをクリックする
③「Generate report」ボタンをクリックする
完了すると、Performance、Accessibility、Best Practices、SEO、Progressive Web Appの5つの指標を評価するレポートが表示されます。
LighthouseではWebページのパフォーマンスだけでなく、開発者やSEOの観点からもWebサイトをチェックできるのが特徴です。
コアウェブバイタルの改善方法
ツールでコアウェブバイタルを確認した後は、先述した目安を参考に、必要であれば各指標を改善しましょう。ここでは、各指標の改善方法について解説します。
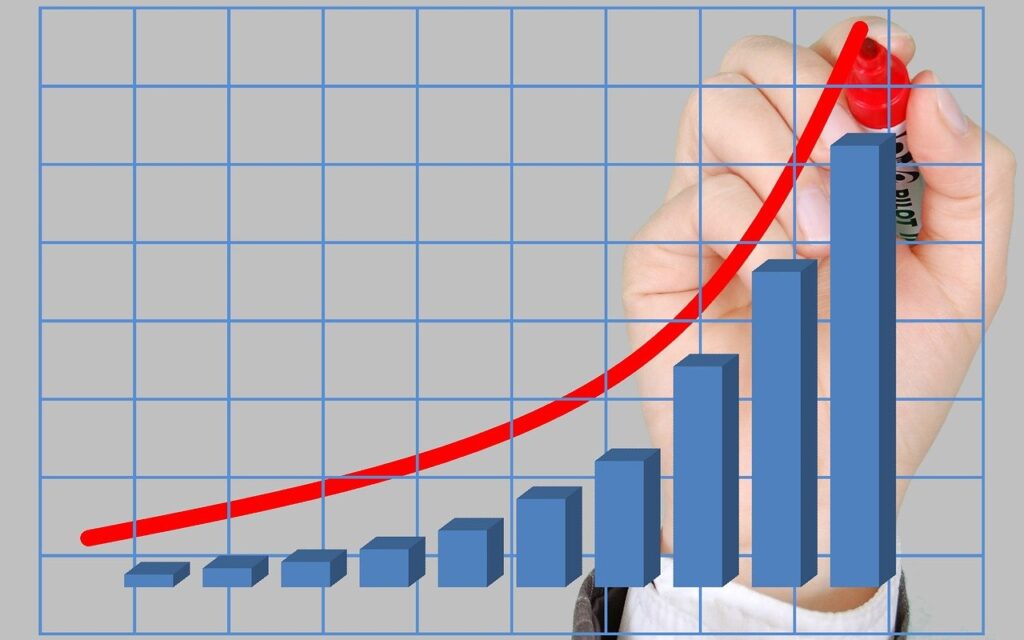
LCP:読み込み速度の改善方法
読み込み速度の低下には複数の要因があるため、LCPはコアウェブバイタルの中でも最も問題が生じやすい指標です。
LCPが低下する主要な原因としては以下のものがあります。
・サーバーの処理が重くなっている
・ブラウザー側の処理が重くなっている
・CSSとJavaScriptが読み込みを阻害している
・ファイルが大きすぎて読み込みに時間がかかっている
改善方法は大まかに次の通りです。
・高性能サーバーに移行する
・JavaScriptの処理に優先順位を付けて実行を最適化する
・CSSをインライン化やJavaScriptの非同期読み込みを実装する
・画像やリソースを圧縮し、不要ファイルを削除する
LCPの改善にはサーバー・ブラウザーの高速化やリソースの最適化が求められます。
CLS:視覚的安定性の改善方法
CLSの改善は、ページの読み込みや操作の最中に発生するレイアウトの変更を最小限に抑えることが重要です。
CLSが低下する主要な原因としては以下のものがあります。
・画像や広告のサイズが指定されていない
・動的コンテンツを多用している
改善方法は大まかに次の通りです。
・画像や広告のサイズを事前に指定する
・ユーザーの操作なしに追加される動的コンテンツ(ポップアップや通知バナーなど)を慎重に管理する
・動的コンテンツを追加する際はスムーズに表示するためにあらかじめレイアウトを確保しておく
CLSの改善には、画像・広告のサイズを事前に指定し、動的コンテンツの管理を徹底することが求められます。
INP:インタラクティブ性の改善方法
INPの改善は、迅速かつスムーズなユーザー体験を提供するために、処理の最適化や遅延の最小化を図ることが重要です。
INPが低下する原因には以下のものがあります。
・不要なJavaScriptが多い
・特定のタスク処理が重い
・複雑なレンダリング処理がある
改善方法は大まかに次の通りです。
・使用しないコードを削除する
・ページ読み込み中に不要なJavaScriptを遅延読み込みに設定する
・処理に時間がかかっているタスクを発見して分割などの最適化をする
INPの改善には、効率的なコード実行やタスク最適化が求められます。
必要に応じて各指標を改善し、コアウェブバイタルの水準を保ちましょう。
コアウェブバイタルと同じくページエクスペリエンスに関連した指標

コアウェブバイタルはより具体的に分類するなら、UXの一部であるページエクスペリエンスを測る指標です。ここでは、同じくページエクスペリエンスに分類される指標を紹介します。コアウェブバイタルを改善したのにWebページの利便性・安全性に問題がある場合は、これらの指標を改善しましょう。
HTTPS
HTTPSは、Webサイトとユーザー間の通信を暗号化するセキュリティプロトコルです。暗号化によって、個人情報が盗まれるリスクを軽減できます。
HTTPを安全に使うための仕組みで、このセキュリティがないと「保護されていない通信」と表示され、ユーザーの信頼を損なう可能性があります。Googleが設定したランキング要因の一つでもあり、検索順位にも影響を与えます。
サイト全体をHTTPS化すれば、セキュリティの安全性をアピールすることができ、結果としてユーザー体験が向上します。
モバイルフレンドリー
モバイルフレンドリーは、モバイル端末(スマホやタブレットなど)からサイトを閲覧したときの見やすさ、使いやすさを評価する指標です。
この指標が低いと、モバイル端末からは文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりなど使いづらいサイトになっている可能性があります。近年はPCよりモバイル端末からサイトを閲覧するユーザーが多いため、ページエクスペリエンスの中では特にSEOへの影響力が高い指標です。
改善することでモバイル端末からの利便性が向上し、ユーザーの滞在時間の向上、離脱率の減少が期待できます。
インタースティシャルの有無
インタースティシャルとは、Webサイトを表示した直後に、コンテンツを隠したり覆ったりする形で表示される広告のことを指します。
ユーザー体験を悪化させる要因となるため、UXの観点ではインタースティシャルは無い方が好ましいです。とくにモバイル端末では画面全体が広告に覆われてしまうことが多いため、ユーザビリティを大きく損なう可能性があります。Googleも不要なインタースティシャルをランキング低下の要因としています。
インタースティシャルを排除することで、ユーザーの滞在時間の向上、離脱率の減少が期待できます。広告が必要な場合は、非侵入型のポップアップやバナー広告を活用することをおすすめします。
セーフブラウジング
セーフブラウジングは、Webサイト内でユーザーに損害を与える恐れがあるコンテンツが含まれていないか調査するサービスです。たとえば、サイトがハッキングされていないか、フィッシング詐欺やマルウェアの配布がされていないか、などを調べます。Googleクローラーの検出やユーザー報告、機械学習による解析などを活用した安全対策システムで、マルウェア感染サイトなど不正サイトにアクセスした時に、ブラウザ上に警告を表示させます。
セーフブラウジングの警告表示は、サイト運営側から見れば「自サイト内に何らかのセキュリティリスクがある」ということです。UXの観点からは、警告の表示対象にならないことが大切です。Googleの規約通りに運営しているサイトであれば、ハッキングや意図しない不正コンテンツの埋め込みがない限りは、対象になることは少ないでしょう。
まとめ
コアウェブバイタルはユーザー体験を向上させるために用いられる指標です。ユーザー体験はSEO達成に重要な役割を果たす一方で、必ずしも優先すべき事項ではありません。コアウェブバイタルを完璧にしようとするのではなく、一定水準を満たした後は、サイト評価の主体となる良質なコンテンツの作成などの他施策に注力することが大切です。
2024年に「FID」が「INP」に改定され、より基準が精密化しています。完璧を目指す必要がない一方で、水準を満たすこと自体の重要性は以前より増しています。コアウェブバイタルがSEOに及ぼす影響は、自サイトの状況次第といえます。状況把握のためにコアウェブバイタルは定期的に測定し、必要に応じて改善策を実施しましょう。


