COLUMNコラム
【SEO最適化】目的達成を可視化するカスタマージャーニーとは? 基本的な作成方法とモデルを紹介
SEOは検索順位を上げるためだけの施策と思われがちですが、SEOの最終目的はコンバージョン(成果)です。単に検索順位を上げるだけでは、SEOの最適化は達成できません。
そこで、活用したいのがカスタマージャーニーです。カスタマージャーニーとは、顧客の購買プロセスを可視化するための概念です。SEOに取り入れることで、顧客のフェーズと合致した対策が取れるようになります。
この記事では、カスタマージャーニーの基本的な作成方法とモデルを紹介します。サイトの検索順位は上がっているのに今一つ成果が上がっていない、とお悩みの方はぜひ記事をご参照ください。
カスタマージャーニーとは
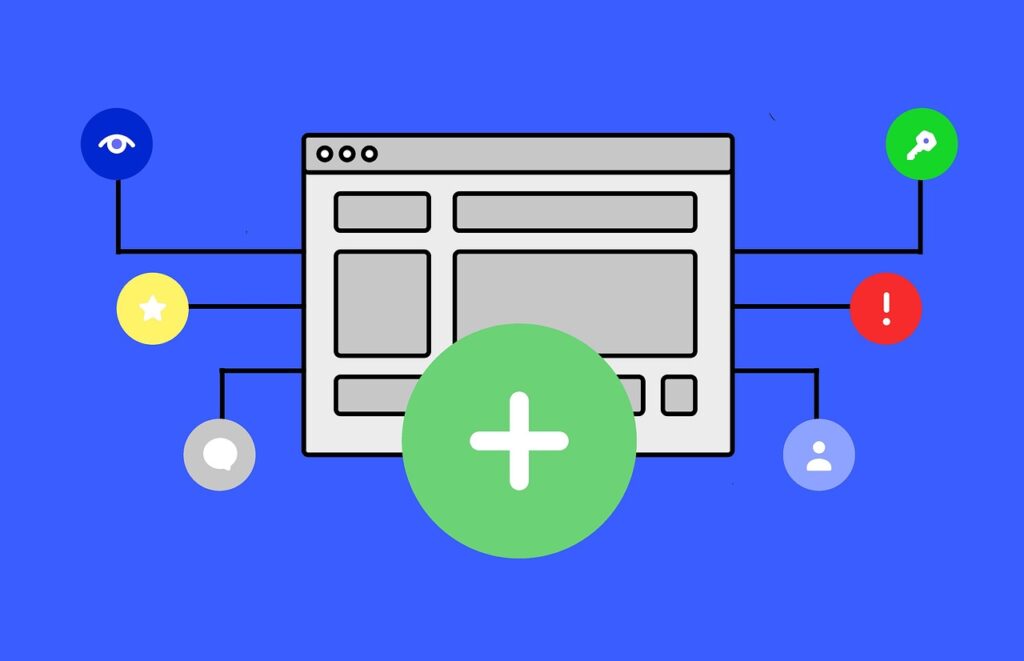
カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知・購入・再購入するまでのプロセスです。
マップ化することで、顧客の行動、感情、思考がフェーズごとにどう変化していくかが可視化され、タッチポイント(顧客接点)に沿った施策を考案するのに役立ちます。
ここでは、カスタマージャーニーをマップ化する目的とメリットについて解説します。
カスタマージャーニーマップを作成する目的
SEOにおけるカスタマージャーニーマップの作成目的は、顧客とのタッチポイントを洗い出し、段階ごとに適切な施策を取ることにあります。
たとえば同じ顧客でも、まだ自社の商品やサービスを知らない段階と、自社の商品やサービスを知っている段階とでは、効果的なアプローチ方法は異なるはずです。
カスタマージャーニーマップを作成し、顧客が購入・再購入に至るまでの行動、感情、思考の流れを可視化することで、段階ごとに適切なアプローチができるようになります。
段階ごとに最適なタッチポイントを提供し、サイト全体の顧客体験を向上させるのが、SEOにおけるカスタマージャーニーマップの作成目的です。
カスタマージャーニーマップのメリット
カスタマージャーニーマップを作成するメリットは主に次の3つです。
- 顧客理解度の向上
- ユーザーファーストな施策の立案
- 社内での認識共有
カスタマージャーニーマップを作成すると、時系列に沿って顧客の行動、感情、思考が予測できるようになり、顧客理解度が向上します。
理解が深まることで顧客が何をしてほしいか具体化し、時系列に沿った情報提供など、ユーザーファーストな施策の立案ができるようになります。
また、認識を共有できることで、関係者の間で生じるズレを最小限に抑え、一貫性のある施策をスムーズに実行できるようになるのもメリットです。
カスタマージャーニーマップを作成することで一貫した顧客視点を得られ、検索順位とは別方向からコンバージョン率の向上が狙えるようになります。
SEOでカスタマージャーニーを活用する効果

具体的にカスタマージャーニーは、どのようにコンバージョン率の向上に貢献するのでしょうか?
SEOでカスタマージャーニーを導入することで期待できる効果は、次の2つです。
- キーワード選定の精度向上
- 顧客体験の向上
ここでは、それぞれを解説します。
キーワード選定の精度向上
カスタマージャーニーを活用することで、顧客視点に寄り添ったキーワード選定が可能になります。
キーワード選定は、分析ツールで検索ボリュームや競合を調査して行うことが基本です。検索エンジンの仕組み上、検索されやすい、上位表示されやすいワードを特定することで、どのキーワードを選択すればサイトのアクセス数を伸ばせるかを考えます。
しかし、アクセスを集められるキーワードが、必ずしも顧客のニーズや検索意図と一致しているとは限りません。そのため、検索順位が高くても顧客の満足度が低く、コンバージョンにつながらない可能性があるのです。
一方で、カスタマージャーニーマップを活用すれば、顧客のニーズや検索意図をカバーできます。段階に応じた行動パターンや感情の移り変わりに着目すれば、ターゲットが求めている情報が具体的になり、より顧客に寄り添ったキーワード選定が可能です。
キーワード選定の精度向上はより効果的なSEO戦略に繋がり、結果としてコンバージョン率の向上に貢献します。
顧客体験の向上
カスタマージャーニーを取り入れてコンテンツを作成すれば、顧客体験の向上が期待できます。
時系列に沿った顧客の傾向をマップ化できれば、購買行動を後押ししている心理・思考への理解を深めることが可能です。理解が深まることで、具体的な問題点や解決策が見えるようになり、顧客の心理に寄り添った施策が打てるようになります。
たとえば、SEOでは顧客の段階的なニーズに合わせた情報提供が代表的です。適切に施策をすれば、コンテンツを通して顧客に「自分の立場を理解してくれている」といった安心感や信頼感を与えることができ、顧客体験が向上します。
顧客体験が良いほど顧客は長期的な関係を築きたいと考えてくれます。これも、コンバージョン率の向上につながります。
カスタマージャーニーマップの基本的な作成方法
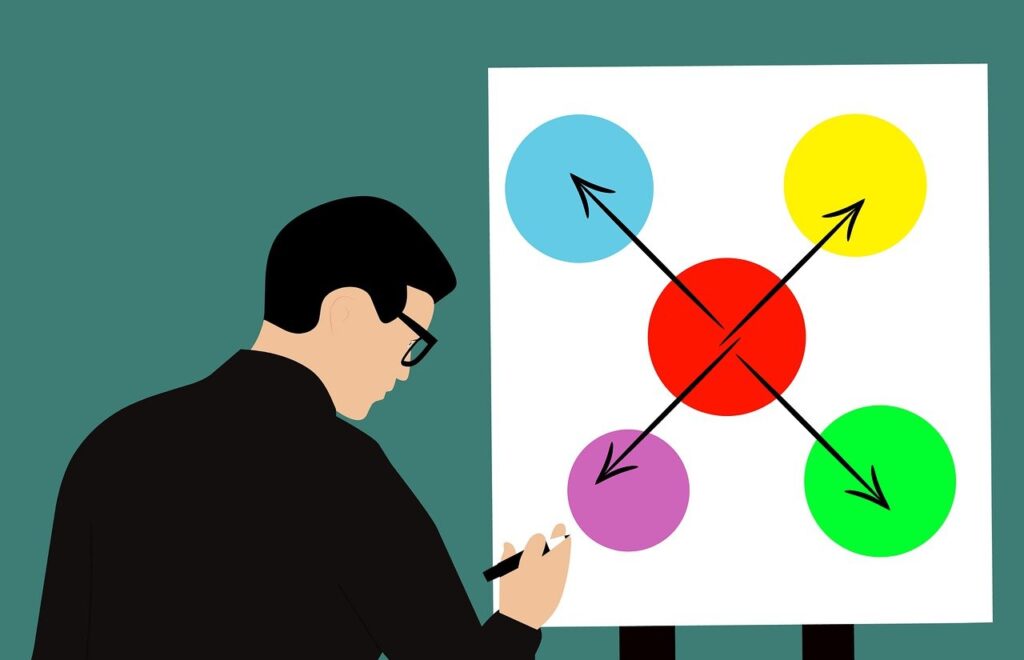
カスタマージャーニーがSEOの最適化に大きく貢献することがわかりました。
どうすれば、カスタマージャーニーマップを作成できるのでしょうか? ここでは、基本的な作成方法を解説します。
ペルソナを設定する
まずは、ターゲットを具体化するペルソナ設定です。
マーケティングにおけるペルソナとは、『商品の購入やサービス利用を行う架空の人物像』です。たとえば、時短を売りにした調理家電なら、忙しい主婦にニーズがあると考えられます。このような人物像に詳細な設定を加え、ターゲットを具体化していきます。
設定する内容としては次のような項目があります。
氏名
年齢
性別
居住地
職業
収入
家族構成
趣味
生活スタイル
忙しい主婦のペルソナなら「35歳の共働き女性、IT企業に勤務し、5歳の娘と夫と共に、世田谷区に在住。健康志向で家族との時間を大切にしている。仕事と育児の両立に悩んでいる」といったようになるでしょう。
ペルソナ設定でターゲット像が明確なることで、今後の最終ゴールや施策方針が具体化します。
最終ゴールを設定をする
次に、ペルソナが期待する最終ゴールを設定します。
最終ゴールはビジネスごとに異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
- 商品購入
- サービス契約
- 会員登録
- 無料相談
- アプリインストール
- 店舗への予約
ゴールを設定することで、達成までの過程を計画しやすくなります。また、ゴールの内容によっては、既存のモデルをそのまま適用できることもあります。
カスタマージャーニーマップを作成する前に、まず最終ゴールを明確にしましょう。
マップの横軸(フェーズ)と縦軸(顧客心理)を設定
ターゲットと目的が決まったら、マップの横軸と縦軸を設定します。
| フェーズ | 認知 | 検討 | 購入 | 利用 |
|---|---|---|---|---|
| 感情 | ||||
| 行動 | ||||
| 課題 | ||||
| タッチポイント |
横軸には、フェーズを書き込みます。たとえば、商品やサービス購入であれば、認知段階・検討段階・購入段階・利用段階などです。
縦軸は顧客理解に必要な項目を書き込みます。たとえば、感情・行動・課題・タッチポイントなどが代表的でしょう。
横軸、縦軸に設定する項目は、ペルソナやゴールの設定次第なので、自由に決めることができます。設定に迷った際は、テンプレートとして使える購買行動モデルがあるので、そちらを参考にしましょう。購買行動モデルについては後述します。
マップ要素をペルソナの視点で埋める
横軸と縦軸の項目が決まったら、マップ要素をペルソナ(顧客)視点で埋めていきます。
この際、売り手側の先入観や願望が混じらないように注意しましょう。顧客視点でフェーズごとの行動・心理をマップ化することが大切です。
たとえば、ビジネスが時短調理家電の販売で、ペルソナが忙しい主婦なら、マップは次のように埋まるでしょう。
| フェーズ | 認知 | 検討 | 購入 | 利用 |
|---|---|---|---|---|
| 感情 | 忙しくて食事準備が大変と感じる | 便利そうだが本当に使いこなせるか不安 | 期待と価格のバランスを考えながら決断 | 便利さを実感しつつ、さらに使いこなしたい |
| 行動 | SNSから情報収集 | Webでレビューをチェック、比較サイトを見る | 公式サイトやECサイトで価格や特典を確認 | 実際に調理し、使い方を模索 |
| 課題 | どの時短調理家電が本当に役立つかわからない | 忙しい中で新しい家電を使いこなせるか不安 | 価格が高いため、コスパが気になる | 期待通りの時短効果があるか、どのようなレシピで使えるか |
| タッチポイント | SNS、YouTube広告 | 口コミサイト、ECサイト、公式サイト | 家電量販店、ECサイト、ブランド公式サイト | 説明書、レシピサイト、ユーザーコミュニティ |
このように、ペルソナの行動や心理を予測・整理できることで、各段階で適切な施策や改善点を導きやすくなります。
ユーザーの行動フェーズの見本となる購買行動モデル
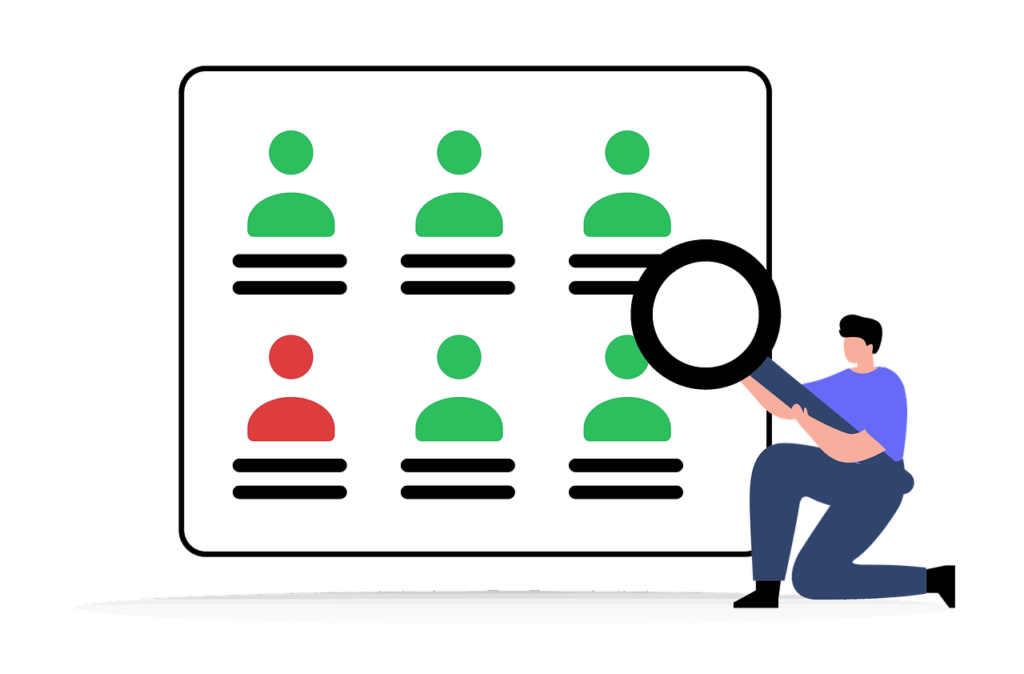
作成例から見てわかるように、カスタマージャーニーマップの構造は、ペルソナやゴールの設定次第でいくらでも変化します。それだけに、初めは何を書くべきか迷ってしまう方も多いです。
そこで役立つのが、ユーザーの行動フェーズの見本となる購買行動モデルです。購買行動モデルとは、消費者が商品やサービスを認知し、購入に至るまでの一連のプロセスを段階的に示したものです。この流れを理解することで、カスタマージャーニーの各段階における顧客の心理や思考を具体的に記述できるようになります。
ここではカスタマージャーニーマップの作成に役立つ購買行動モデルを3つ紹介します。
AIDA(マスメディア広告向け)
AIDA(アイダ)は消費者の購買行動を「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Action(行動)」の4段階に分けたフレームワークです。
消費者心理の基本に沿った設計で、シンプルで理解しやすく、広告やセールスなど広範囲に活用できます。
一方で、まだテレビが普及していない1920年代に提唱されたモデルであり、どちらかというとマスメディア広告向けです。インターネット時代のマーケティングで活用するにはシンプルすぎて、不十分な場合もあります。
AIDAは基礎として押さえつつ、現代の消費行動と組み合わせて活用しましょう。
AIDMA(テレビ・雑誌広告向け)
AIDMA(アイドマ)は消費者の購買行動を「Attentio(注意)」「Interest(関心)」「Memory(記憶)」「Desire(欲求)」「Action(行動)」の5段階に分けたフレームワークです。
AIDAに「Memory(記憶)」の段階が加わることで、消費者の購買行動における時間の概念が、より明確になりました。これにより、広告を見た後、商品やサービスを記憶し、後日、必要になった時に購入するという、中長期的な購買行動を考慮できるフレームワークになっています。
ただし、こちらも1920年代に提唱された古いモデルで、どちらかというとテレビ・雑誌などのマスメディア広告向けです。現代では、インターネット検索で調べればすぐに情報が得られるようになっているため、記憶の重要性はやや下がっています。
AIDMAも基礎として押さえつつ、現代の消費行動と合わせて活用しましょう。
AISAS(インターネット広告向け)
AISAS(アイサス)は消費者の購買行動を「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Search(検索)」「Action(行動)」「Share(共有)」の5段階に分けたフレームワークです。
インターネットを利用した情報検索、商品比較の行動を中心に構築されているため、オンライン広告やSEO、SNS活用など現代的なマーケティング戦略に適しています。口コミやソーシャルメディアの情報共有(Share)の影響力を反映しているのが大きな特徴です。
一方で、インターネットを前提とした購買行動モデルであるため、伝統的なマスメディアを利用する顧客層には効果を見込めない可能性があります。ターゲットの年齢層によっては、注意が必要でしょう。
AISASは現代に適した購買行動モデルですが、すべての消費者に当てはまるわけではありません。過信はせず、ターゲット層を見極めて活用することが大切です。
SEO対策への活用方法

購買行動モデルをお手本にすることで、顧客の行動・心理が理解しやすくなり、スムーズにカスタマージャーニーマップを作成できるようになります。
作成したマップは、SEOでどのように活用できるのでしょうか?
ここでは、カスタマージャーニーマップをSEO対策に活用する方法について解説します。
検索意図の設定
カスタマージャーニーマップを活用することで、ユーザーの検索意図をより把握しやすくなります。
検索意図はGoogleが提唱する検索意図の4分類である「Know・Go・Do・Buy」クエリを参考にするのが基本です。
Know:情報を知るために検索する
Go:特定のサイト・実在する場所へ行くために検索する
Do:行動するために検索する
Buy:商品やサービスを購入したいから検索する
4つのクエリを考える際にカスタマージャーニーマップを活用すると、ユーザーがどの段階でどんな情報を求めているかを明確にできます。たとえば、「Know」クエリであれば、ペルソナの感情や課題から、具体的な検索ワードを想定しやすくなるでしょう。
カスタマージャーニーマップをSEOに組み込むことで、ユーザーの心理・行動の変遷を検索意図に反映させやすくなります。
検索ニーズの設定
カスタマージャーニーマップを作成することで、ペルソナの行動・心理に基づいて段階的な検索ニーズが設定できるようになります。
マップを見るとわかると思いますが、ユーザーの検索ニーズは段階を経て変化します。この段階ごとのニーズを満たしていくのが、コンバージョン達成のセオリーです。
たとえば、コンバージョンが「商品の購入」であれば、大まかに認知・検討・購入の三段階の検索ニーズを満たす必要があるでしょう。
具体的には、認知・検討段階で検索ニーズを満たして見込み客を増やし、その見込み客を対象にして、購入段階の検索ニーズを満たします。見込み客になってもらう段階を経ずに、いきなり商品を購入してもらうのは難しいため、顧客のニーズを段階的に満たしていく必要があるのです。
カスタマージャーニーマップを活用すれば、ペルソナの行動・心理の段階的な変化を具体化できます。フェーズごとの検索ニーズが把握しやすくなることで、コンバージョン達成の道筋を立てることができます。
検索キーワードとコンテンツの設定
カスタマージャーニーマップを作成することで、検索キーワードとコンテンツの整合性を高められます。
ユーザーの検索意図を満たすためには、検索キーワードとコンテンツの内容が一致していることが重要です。
たとえば、認知段階にある顧客は、自分の悩みを認識し、解決するための選択肢を求めています。このような段階で出す検索キーワードに対して、いきなり自社製品をアピールする情報コンテンツを提供しても、購入してもらえる可能性は低いでしょう。
カスタマージャーニーマップを活用すれば、顧客の行動や心理をフェーズごとに把握し、それに合ったコンテンツを設定できます。これにより、検索とコンテンツの整合性が向上し、よりユーザーが求める情報を提供しやすくなります。
効果検証→改善のサイクル
顧客体験を可視化できるカスタマージャーニーマップは、効果検証と改善のサイクルを円滑化するのにも役立ちます。
SEOの本来の目的であるコンバージョンを達成するには、より広い視野で施策を行う必要があります。そのため、施策が広範囲に及び、全体像が把握しにくくなりがちです。
カスタマージャーニーマップを活用すれば、顧客のフェーズごとのSEO施策や実施状況を視覚的に把握できるようになります。一目で効果が出ているかわかるため、他者とすぐに状況を共有でき、改善のための議論や検討の効率化できます。
カスタマージャーニーマップを作成するときの注意点

カスタマージャーニーマップをSEOに導入することで、より顧客視点に立った施策を実行できるようになることが分かりました。
一方で、実用性のあるカスタマージャーニーマップの作成には条件があります。最後に、作成時の注意点を3つ紹介します。
他部署と連携する
実用性の高いカスタマージャーニーの作成には多角的な視点が不可欠です。単一的な視点ではニーズや課題を正確に把握できません。できればマーケティング部署内だけでなく、他部署のメンバーも巻き込みましょう。とくに顧客と接する機会がある営業や販売、カスタマーサポートはおすすめです。
違う視点を持った複数人が意見を出し合って作成することで情報の精度が高まり、顧客の隠れた本音を見つけ出せるようになります。他部署と連携して、顧客解像度の高いカスタマージャーニーを作成しましょう。
顧客視点で作る
カスタマージャーニーの作成でよくある失敗は「顧客がこうなってくれれば助かる」といった制作側の願望が混じってしまうことです。制作側の願望が混じってしまうと、顧客の実態とかけ離れたマップになってしまい、目的を達成できません。作成時は思い込みや偏見がないか自問自答し、顧客視点とズレていないか確認しましょう。
顧客視点のズレを防止する面でも、互いを監視し合える他部署と連携は効果的です。願望を抜きにして、顧客視点を徹底したカスタマージャーニーを作りましょう。
検証・修正を続ける
カスタマージャーニーは作り終えた後も、検証・修正を続けることが大切です。カスタマージャーニーは一度作れば機能するというものではなく、改善サイクルを通じて精度を高めていく必要があります。
また、情報が氾濫する現代において、ユーザーの購買行動は常に変化していきます。精度が向上した後も検証・修正を行っていかないと、やがて顧客と施策にズレが生じて、実用性が失われてしまいます。
カスタマージャーニーには定期的なアップデートが不可欠です。できれば、四半期に一度は見直す機会を設けて、実用性の維持に努めましょう。
まとめ
カスタマージャーニーは顧客理解度を促進させ、ユーザーファーストなコンテンツを作成するのに役立ちます。SEOに組み込むことで、顧客視点での対策が可能になり、コンバージョンを達成しやすくなります。
検索上位なのに成果が上がっていないサイトは、ユーザーの検索意図や行動とマッチしていない可能性が高いです。コンバージョンを達成するためにも、カスタマージャーニーを活用して、SEOの最適化を目指しましょう。


