COLUMNコラム
SEOにプラスして実施すべきAEOとは? 必要性が高まる背景と基本対策を解説
SEO(Search Engine Optimization/検索エンジンの最適化)は上位表示を達成して、コンテンツを「読んで」もらうことを前提とした施策です。しかし、近年は検索ユーザーの行動が変化しています。単にサイトを探すのではなく、検索結果のページそのもので 「質問に対する答え」 を求めるケースが増えてきました。
そこで注目されているのが AEO(Answer Engine Optimization/応答エンジンの最適化) です。AEOは「読ませる」のではなく「答える」ことに焦点を当て、ユーザーが最短で疑問を解決できるようにするための考え方です。
本記事では、SEOにプラスして実施すべきAEOの基本を初心者向けにわかりやすく解説します。マーケティングやサイト対策をする上で必要性が高まる背景や、実際に取り組める基本対策について整理していきましょう。
AEOとは?

AEO(Answer Engine Optimization/応答エンジン最適化) とは、検索エンジンやAIがユーザーに「最適な答え」を直接返せるようにするための最適化のことです。
現時点でサイト対策の主流であるSEOは、検索結果の上位に自分のサイトを表示させ、クリックしてもらうのが目的です。一方、AEOは 「検索結果ページの中で答えを提示する」 ことを重視します。
たとえば「東京駅近くのカフェ」と検索したときに、Googleマップに自社店舗の情報(住所・営業時間・口コミ)が直接表示されれば、画面を見るだけで「ここに行こう」と判断できます。これがAEOの理想とする検索結果です。サイトをクリックされなくても、実際の来店や利用につながる効果が期待できます。
つまり、
SEO → 自社ページをクリックして見てもらうための最適化
AEO → 検索結果のみ(ゼロクリック)で自社情報を表示させるための最適化
という違いがあります。検索体験が「調べる」から「すぐ答えを得る」方向へ進化している現在、AEOは欠かせない取り組みになりつつあります。
AE(応答エンジン)の種類
AEOの対象となる応答エンジンには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか? 応答エンジンの範囲は広いですが、マーケティングやWebサイト対策では次の3種が重要になります。
- 検索エンジンの各機能(アンサーボックス / 強調スニペット/ AIによる概要)
- 対話型AI(ChatGPT / Gemini / Perplexity / Copilot)
- 音声アシスタント(Siri / Alexa / Google Assistant)
各応答エンジンの概要と最適化のメリットは以下の通りです。
- 検索エンジンの各機能(アンサーボックス / 強調スニペット / AIによる概要)
GoogleやBingなどの検索結果の上部に表示される「答え枠」です。たとえば「AEOとは?」と検索したときに、AIによる概要(AI Overview)が検索結果のトップに表示されます。情報源リストに自社サイトが掲載されれば、ユーザーはクリックせずとも自社サイトの名前やURLを目にします。これは記事やブログを運営している場合、特に有効です。 - 対話型AI(ChatGPT / Gemini / Perplexity / Copilot)
対話型AIはユーザーの質問に対して検索結果を要約し、対話形式で答えるシステムです。最近では回答に、情報源として引用しているサイトを明示することもあります。自社の記事やコンテンツが信頼できる情報として選ばれれば、回答に自社名やURLが掲載される可能性があります。認知度や流入の向上が期待できるでしょう。 - 音声アシスタント(Siri / Alexa / Google Assistant)
スマートフォンやスマートスピーカーに「近くの○○」「△△とは?」と質問したときに、検索エンジンの情報を元に音声で返答します。自社の店舗情報やサービス内容が読み上げられれば、ユーザーに直接選ばれるチャンスになります。ローカルビジネスや日常利用されるサービスでは、特に効果的です。
応答エンジンによって提供される機能は利便性が高く、利用者も右肩上がりで増え続けています。
AEOがなぜ重要か?
応答エンジンがもたらす利便性はGoogleが重視する「ユーザーファースト」の理念とも一致するため、今後さらに発展していくでしょう。しかし、これはコンテンツを「読ませる」という工程を省き、直接「回答」を提供することを強化していくのに他なりません。つまり、Googleがユーザーファーストを推し進めるほど、SEOだけではWeb集客が難しくなる可能性が高いのです。
実際に、アメリカの有名なSEO専門ニュースサイト「Search Engine Roundtable」では、Web分析大手「Similarweb」のレポートを引用し、
「2024年5月にGoogle AI Overviews(AIによる概要)が開始されて以来、ゼロクリック検索は2025年5月には56%から69%へと13ポイント増加した」
と伝えています(参照:Search Engine Roundtableの記事)
つまり、現在のアメリカでは既に約7割近いユーザーが、サイトをクリックせずに検索を終えてしまっているということになります。このような状況下で「答える」ことに焦点を当てたAEOは、SEOの影響力減少に反比例して重要性が高まっています。
AEO対策の必要性が高まる背景

どうしてSEOの影響力が下がっているのでしょうか?
大きな理由として挙げられるのは、ユーザー行動の変化とそれに伴うテクノロジーの進化です。ここでは、AEO対策の必要性が高まる背景を3つ解説します。
検索行動が「回答重視」に変化
1つ目は、ユーザーの検索行動が、キーワードの入力のみで直接的な回答を求める「回答重視」に変化したことです。
従来の検索行動は「情報を探す」ことが主目的でした。しかし、近年は「短時間で答えを得たい」というニーズが強まっています。たとえば「食事 カロリー 計算方法」と検索するのではなく「ジャガイモ1個のカロリーは?」と直接質問する人が増えています。つまり、ユーザーは「記事を読んで答えを出す」ためではなく、「必要な答えを一瞬で得る」ために検索行動をとるようになっているのです。
こうした行動に応えるために、検索エンジンはアンサーボックスや強調スニペットなど「即時に回答する」仕組みを強化しています。特に、近年ではAIによる概要(AI Overviews)が導入され、質問形式でワードを入力すると複数サイトを要約した回答が表示されることが多くなりました。
単に記事を公開するだけでは選ばれにくくなり、読者に「直接回答を提示できる形」を整えるAEO対策が必須になっています。
スマホ普及による音声検索の一般化
2つ目は、音声検索の一般化より会話形式の検索が増え、簡潔で直接的な回答の提供が求められるようになったことです。
検索はスマホの普及で検索は「調べる」から「質問する」へと移行しました。これにより、複数の選択肢を提示するよりも「最も的確なひとつの答え」を返すことが求められるようになっています。
実際に、Siri、Google Assistant、Alexaなどの音声アシスタントは、検索結果を一覧表示するのではなく「ひとつの答え」を読み上げます。この仕様のため、音声検索で選ばれる情報になることが競争上の大きなポイントになっています。
情報を網羅的に伝えることを良しとしているSEOとは対極的です。モバイル・音声環境で選ばれるには、AEO対策が不可欠になっています。
生成AIの進歩
3つ目の背景は、生成AIがユーザーの質問に対して、会話形式で的確な回答を返せるようになってきたことです。
ChatGPTやGeminiといったAIの普及により、ユーザーは「検索で情報を集める」よりも「AIに直接尋ねる」行動をとるケースが増えています。情報収集の流れが「複数のサイトを回る」から「AIにまとめてもらう」へとシフトしているのです。
生成AIは複数の情報源を整理して自然な文章で答えを生成し、さらに最近では引用元を併記する機能も強化されています。つまり、AIに「信頼できる情報源」として選ばれることが、自社コンテンツの露出機会に直結するようになっています。
ユーザーが直接サイトを訪れる回数は減少していく傾向です。AEO対策をしないと、自社情報がユーザーの目に届かないリスクが高くなります。
AEOとSEOの関係

SEOが対象としてきた「サイトをクリックして情報を探す」というユーザー行動が減少し、AEO対策の必要性が高まっていることが分かりました。
しかし、だからといってAEO対策がSEO対策にとって代わるわけではありません。両者は異なる対策で、相互扶助の関係にあります。以下は、SEOとAEOを比較した表です。
このように、両者は目的も対象も異なります。AEOは、SEOとは別領域でプラスして実施すべき対策といえるでしょう。
その一方で両者には、共通する部分もあります。
それは、ユーザーの検索意図を理解し、E-E-A-Tを満たした情報を提供することです。
E-E-A-Tは、コンテンツの質を評価する際にGoogleが重視する4つの指標、経験・専門性・権威性・信頼性の略です。これらの指標は、コンテンツがユーザーにとって本当に役立ち、信頼できるかを判断するために使われます。
SEOで検索順位を上げるためにも、AEOで回答として表示されるためにも、E-E-A-Tへの準拠が不可欠です。どちらも対策の過程でE-E-A-Tを高めるため、結果的にSEOとAEOは相互扶助の関係になります。
AEO対策の考え方
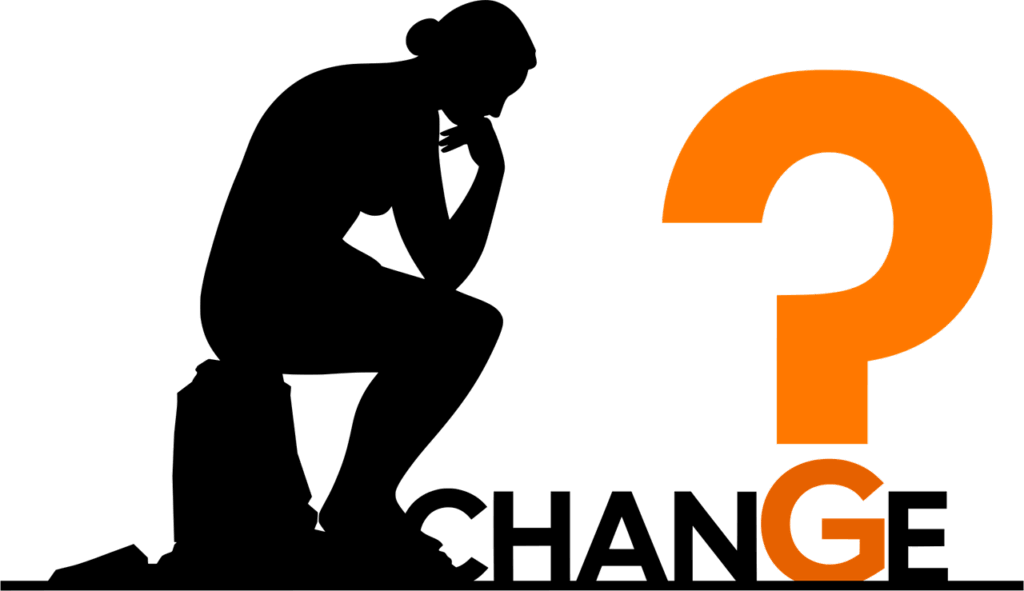
AIは「答え」として参照するコンテンツをE-E-A-Tを指標にして決めています。SEO対策をすることもAEO対策の一環になるでしょう。
とはいえ、SEOに則したコンテンツを提供するだけでは、今までと変わりません。そこで、ここでは、AEO対策で何をすべきか、という考え方を解説します。
検索意図に対して明確な回答を用意する
AEOでは「ユーザーがすぐに疑問を解消できる回答を提示できるか」を優先して評価しています。短時間での直接的な回答が求められているため、理解を促すためであっても「回りくどい説明」や「前置きの長い記事」では応答エンジンに選ばれにくくなる傾向があります。
明確な回答が用意された形式として分かりやすいのが、Q&Aやよくある質問です。どちらも「ユーザーの疑問に直接的かつ簡潔に答える」というAEOの評価基準に合致しているため、AIに採用されやすいです。記事タイトルや見出しでも、本文で結論を簡潔に結論を提示することで、同様の評価が期待できます。
AEO対策では「問い(見出し)」と「答え(結論)」の関係を出来るだけ明確にしましょう。
自社ならではのオリジナル情報を盛り込む
AIや検索エンジンは、既にWeb上に大量に存在する一般的な情報を要約して提供しています。そのため、他サイトと同じ内容だと競合してしまい、回答に選ばれる可能性が低くなります。逆に、自社独自のデータや事例を交えることができれば情報の新規性・専門性が高まり、競合しないテキストとして引用や掲載される確率が上がります。
競合を避けるためにも、顧客アンケートや自社データなど、競合他社にはない一次情報をコンテンツに組み込みましょう。また、E-E-A-Tを強化するため、専門家による記事監修や執筆協力してもらい、その事実を記事内で明記するのも有効です。
AEO対策では何よりも「信頼できる一次情報」が大切になります。
基本的なAEO対策
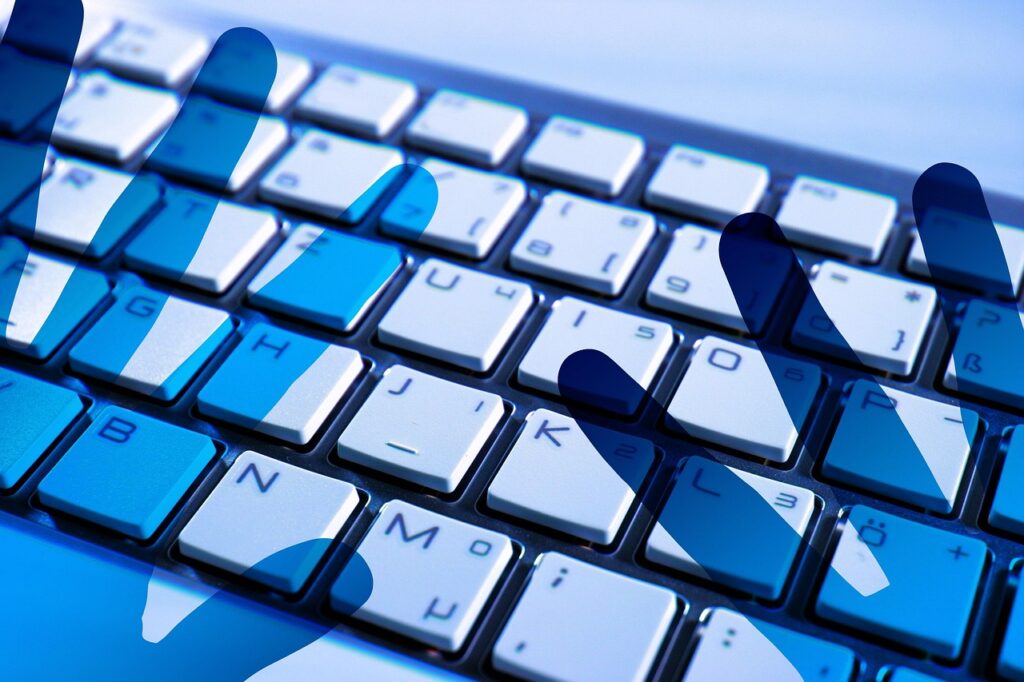
AEOは、明確な回答を提示できる構造と信頼できる一次情報によって成り立つとわかりました。では、そのために具体的に何をすべきなのでしょうか? ここでは、AEOの基本的な対策について解説します。
質問形式を意識したコンテンツ作成
質問形式とは、ユーザーが実際に検索で入力するような質問文を見出しや小見出しに設定し、それに対して明確な回答を本文で提示するような形式です。たとえば、「SEOとは何か?」や「初心者向けのSEO対策は?」といった見出しに対し、本文でその問いに対する回答を記述します。
応答エンジンは質問形式の検索意図を理解し、それに合致した回答を優先して表示する仕組みです。そのため、検索意図に直接マッチした見出しと回答を持つコンテンツはAIに採用されやすくなります。
質問形式を意識したコンテンツ作成をすることで、応答エンジンから選ばれる確率が高まります。
FAQ・Q&Aなどの構造化データの活用
構造化データとは、Webページの情報を検索エンジンが理解しやすいように整理するためのデータ形式です。AEOでは、FAQ・Q&Aなどの構造化データを実装することで、検索エンジンにコンテンツが質問形式であると伝わりやすくなります。
構造化データで「名札付け」することでAIや検索エンジンは、ページ内の質問と回答のペアをより確実に把握できます。結果として、アンサーボックスやAI Overviews、音声アシスタントの回答に採用されやすくなります。
FAQやQ&Aを構造化して提示することは、AEO対策の基本かつ効果的な手法です。
結論ファーストで回答を明確化
コンテンツ作成では、「問い」と「答え」の関係を明確化するために、結論ファーストを心がけます。たとえば、「食べながら痩せるには?」という見出しなら、冒頭で「食べながら痩せるには、咀嚼を意識してゆっくり時間をかけて食事をすることです」とまず結論を述べてから、その結論を補強していくように情報や説明を記述していきます。逆に、長い前置きや導入は、AEOでは評価されません。
応答エンジンは簡潔で明瞭な回答を好みます。結論を最初に提示しておくことで、AIが「答え」として抽出しやすくなり、検索結果に表示される確率が高まります。
結論ファーストの構成は、応答エンジンに選ばれるコンテンツづくりの必須条件です。
信頼性・権威性を示すデータの明示
情報の価値は、発信元の信頼性・権威性の有無で大きく変わります。できるだけ公式機関の統計データや一次情報を引用し、出典を明示しましょう。執筆者の専門性や運営者情報をページに記載することも重要です。
応答エンジンは信頼性と権威性を重視して情報を抽出します。裏付けのあるデータや専門的知見を明示することで、AIに「信頼できる情報源」と認識されやすくなります。
権威性と信頼性を担保した情報提供は、AEOにおいても欠かせません。
モバイル・音声対応への最適化
モバイルファーストを前提にページを設計し、レスポンシブ対応や高速表示を確保します。また、音声検索に対応するために、会話形式の質問や短文回答を意識したコンテンツを作成します。
モバイルファーストも音声対応も、ユーザーの「今すぐ知りたい」「手間をかけずに知りたい」に応える設計です。これは、AEOの価値基準と一致します。両者を前提に設計することが、AEOの評価を高めます。
モバイル・音声対応を前提とした最適化は、現代の検索環境におけるAEO対策の要となります。
まとめ
ユーザーの検索行動は「情報を探す」から「直接答えを得る」方向へシフトしています。
その結果、従来のSEOだけでなく、AEOを意識した対策が不可欠になっています。
SEOとAEOは目的も手法も異なります。しかし、両者はE-E-A-Tを満たす良質なコンテンツを作成する点で共通しており、相互に補完し合う関係です。今後は、SEOを土台としつつ、AEOを追加で取り入れる必要があります。「読ませる」だけでなく「答える」に焦点を当てたWeb集客にも対応できるようにしましょう。

