COLUMNコラム
Web対策としてのLLMOとは? SEOとの関係やAIに引用されるための対策を解説
LLMOとは、生成AIが回答を生成する際に、自社コンテンツが引用・参照されやすくするための対策です。
近年では、キーワード検索を行うだけでAIによる回答が表示されるようになりました。ChatGPTやGeminiといった対話型AIの成長も著しく、対話形式で意図を伝えながら答えを得るユーザーが急増しています。
もはや従来のSEO対策だけでは、ユーザーの情報収集行動に対応できません。AI経由のユーザーを取りこぼさないためにも、今後のWeb対策ではLLMOへの取り組みが不可欠です。
本記事では、Web対策としてのLLMOを初心者向けに分かりやすく解説します。SEOとの関係や具体的な施策を知りたい方は、ぜひご参照ください。
LLMOとは?
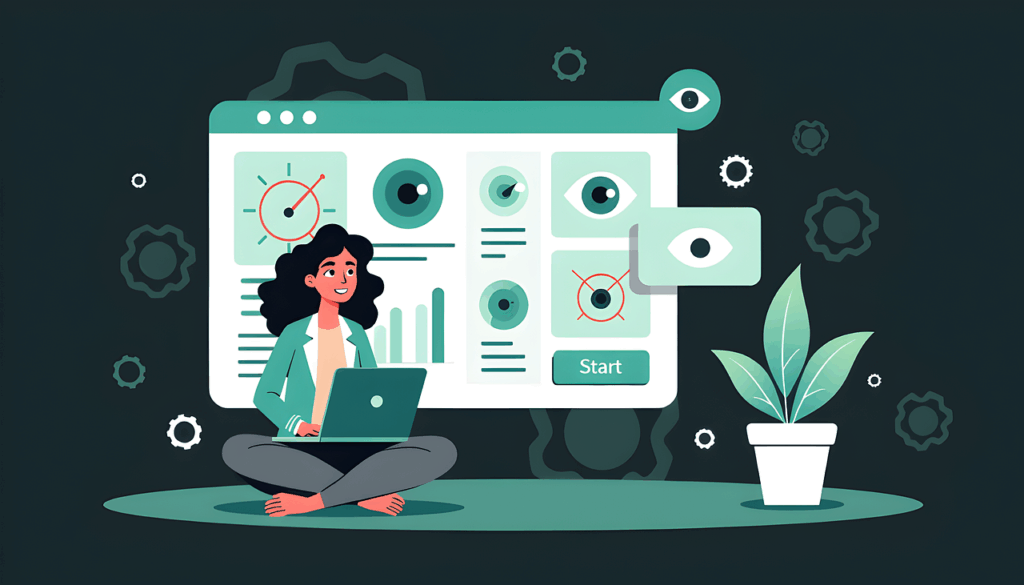
LLMOとは、「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」の略です。生成AIの回答に自社コンテンツを引用してもらうための対策・戦略全般を指します。
具体的には、対話型AI(チャットGPTやGemini)の回答や、Web検索時に表示されるAI Overview(AIによる概要)に自社コンテンツを引用・参照などが挙げられるでしょう。手法は異なりますが「Web上の情報露出」という目的でSEOと一致しています。
ここでは、LLMOを理解するためにLLMの仕組みとその最適化について解説します。
そもそもLLMとは?
LLM(大規模言語モデル)は大量のテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成できるAIモデルです。ただし、本当に言葉の意味を理解しているわけでなく、膨大な学習データから「次に続く言葉のパターン」を統計的に予測して文章を生成しています。
たとえば「今日は天気がとても」というフレーズなら、それに続く単語のパターンは「いい」「悪い」「晴れ」「雨」など無数にあります。その中から、LLMは膨大な学習データを活用して「統計的に適切なパターン」を選別して文章を作成します。
仮に「今日は天気がとても」に続く単語のパターンの統計が以下の通りだったとしましょう。
「今日は天気がとてもいい」→ 60%
「今日は天気がとても悪い」→ 35%
「今日は天気がとても晴れ」→ 4%
「今日は天気がとても暑い」→ 1%
この場合、LLMは確率が高い「今日は天気がとてもいい」を選択して文を作成します。
LLMは「言葉の意味を理解する」というよりも、膨大なデータから「言葉がつながるパターン」を学び、その確率に基づいて文章を作成しています。
この仕組みを利用して自社コンテンツの露出を狙うのがLLMOです。
LLMOは、LLMが次の言葉を予測して文章を組み立てる仕組みを踏まえ、「自社コンテンツがAIにとって統計的に信頼性の高い情報」として選ばれるよう最適化する取り組みを指します。
先ほどの例で「今日は天気がとても」に続く単語として「いい」が選ばれたのは、AIにとって最も信頼できるパターンだったからです。
同じように、LLMOではユーザーの質問に対して、AIが「この情報を使うのが自然で信頼できる」と判断できる文章を整備していくことが重要になります。
LLMの基本的な仕組み「コンテキストウィンドウ」
LLMOで成果を上げるための施策は、大きく2つに大別できます。
①AIが情報を「理解」しやすくする施策
②AIが情報を「信頼」しやすくする施策
②の「信頼」しやすくする施策は、目的こそ異なりますがSEOとほぼ共通です。そのため、LLMOの解説では、①の情報を「理解」しやすくする施策がメインになります。
AIに情報を理解させる上でぜひ知っておきたいのが、LLMの基本的な仕組みである「コンテキストウィンドウ」です。コンテキストウィンドウとは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが、一度に処理できるトークン数(単語、句読点、記号など意味を持つ最小単位)の上限を指します。
この上限を超えてしまうと、AIは古い情報を忘れ、新しい情報のみに基づいて応答を生成してしまいます。これが、AIが文脈を無視した不自然な回答を提示してしまうプロセスです。
そのため、LLMOでは「少ないトークンで多くの情報を渡す」のが基本になります。これは、冗長な表現を避け、簡潔かつ的確に本質を伝えるということです。
分かりやすい例としては、長い前置きや記事の要点ではないトピックの排除・簡潔化などが挙げられるでしょう。無駄にAIのトークンを消費させる要素を無くすことが、AIに選ばれる可能性を高めるのです。
LLMOが注目される背景
LLMOが注目を集めている背景には、生成AIの台頭によって、従来のSEO対策だけではユーザーの情報収集行動に対応しきれなくなっている現状があります。
2022年11月にChatGPTが登場して以来、生成AIのビジネス活用は急速に拡大しました。これに伴い、ユーザーは検索エンジンでキーワードを入力するのではなく、対話型AIに直接質問して回答を得るスタイルへと移行しつつあります。
さらに検索エンジン自体も変化しています。Googleでは「AI Overview(生成AIによる要約表示)」が導入され、ユーザーは検索結果をクリックせずに必要な情報を得られるケースが増えています。このような「ゼロクリック検索」の拡大により、たとえSEOで上位表示を達成しても、従来ほどの流入は期待できなくなっています。
これからのWeb対策は、SEOだけでは不十分です。検索に加えて生成AIからも情報を届けられるようにする施策としてLLMOの必要性が高まっています。
LLMOとSEOの関係

LLMOとSEOは、それぞれ異なる概念ですが、重なる部分も少なくありません。関係性を理解するためにも、両者を比較して違いを明確にしておくことが大切です。LLMOとSEOの主な違いを表にまとめると以下の通りです。
| 項目 | LLMO(LLMの最適化) | SEO(検索エンジンの最適化) |
| 対象 | 大規模言語モデル(LLM) | 検索エンジン |
| 目標 | AI回答に自社情報が引用される | 検索結果で上位表示される |
| 想定する行動 | AIによって生成された回答を見て参照URLからサイトを訪問 | 検索結果を見てタイトルからサイトを訪問 |
| 成果指標 | AI回答での引用・露出回数 | 検索順位・訪問回数 |
| 重視する点 | AIが理解しやすいコンテンツ | ユーザーに信頼されるコンテンツ |
LLMOでは、AIに情報内容と参照価値を正しく理解させる必要があります。わかりやすく参照価値のある情報とは、SEOが達成されてユーザーに信頼されているコンテンツです。
また、SEOでも検索エンジン(AI)に情報を正しく伝える必要があります。「信頼されるコンテンツ」の条件には、LLMOの達成も含まれます。
つまり、両者は目的達成の過程で互いのノウハウを利用することもあるということです。LLMOとSEOは相互補完の関係にあるといえるでしょう。
AIに参照されやくする施策
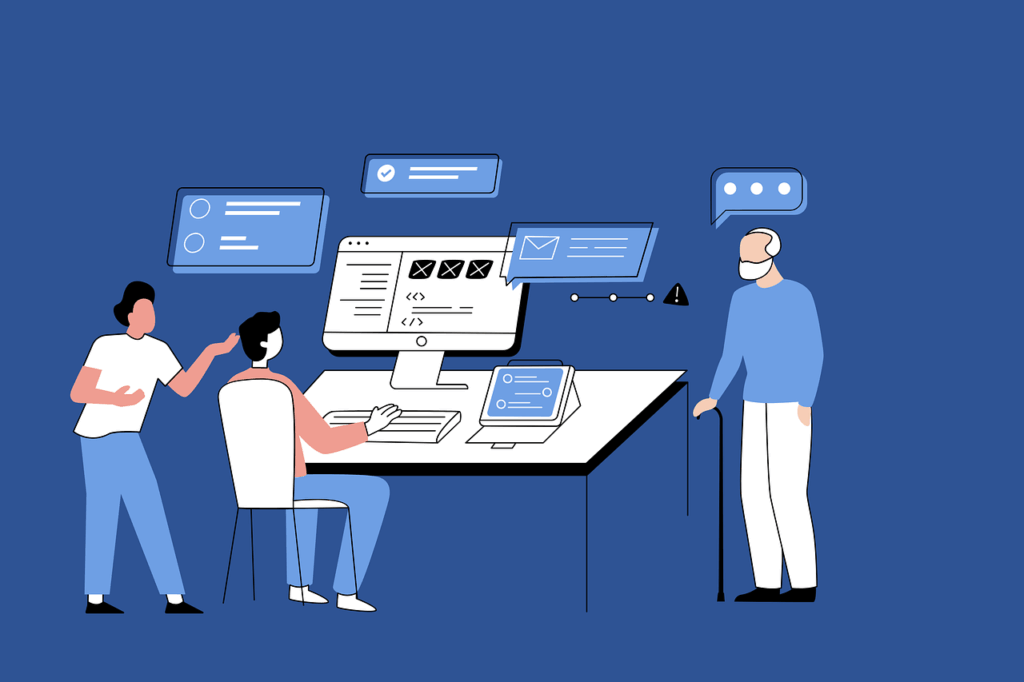
AIにとって価値の高い情報とは、基本的にSEOの要件を満たした情報でもあります。
そのため、LLMOではSEOと共通する施策を取るケースが少なくありません。ここでは、LLMOの中でも特にSEOと重なる部分が多い、「AIに参照されやすい情報」を作るための施策を解説します。
検索での上位表示
AIはネット上の膨大な情報を学習・参照しています。その情報源の多くが検索エンジンから高く評価されたサイト情報です。つまり、検索結果で上位表示されたコンテンツは、AIにとっても「信頼性の高い情報」と見なされやすくなります。SEOで上位表示を狙うことは、AIに参照される確率を高める基本的な施策といえます。
上位表示を実現するには、ユーザーの検索意図に合致した高品質なコンテンツの作成が前提です。ユーザーの疑問を的確に解消できるよう、情報の正確性と網羅性を両立させることが重要になります。この前提を満たせてこそ、後述するE-E-A-T強化を達成できます。
運営元・サイトのE-E-A-T強化
AIは情報の品質だけでなく、その情報源の「信頼性」も重視しています。その信頼の指標として、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は特に重要です。E-E-A-Tの評価が高いほど、AIは「回答に引用しても問題ない確かな情報」と判断しやすくなります。この信頼性は、お金や人生(YMYL)に関わる分野では必須になります。
E-E-A-Tを高める施策としては、透明性や専門性を提示することが基本です。記事の執筆者や監修者の専門性を明記してプロフィールや経歴を公開したり、サイト運営者の企業情報や問い合わせ先を明示したりします。情報の裏付けとなる「誰が」「どのような実績・資格で」発信しているかを明確に示し、信頼を獲得していくことが、E-E-A-Tを向上させる基本になります。
一次情報の発信
AIも検索エンジンも、一次情報を「独自性の高い価値ある情報」として評価します。一次情報とは「自社から発信したオリジナル情報」です。たとえば、自社独自の調査結果やインタビュー、実験データなどがこれに該当します。このような情報はネット上で重複せず、ユーザーに新しい知見を提供できるため、AIから参照・引用される可能性が高まります。
一次情報の発信では、自社でインタビューやアンケート調査を実施します。参照されやすくするには、先述した通りE-E-A-Tが重要になるので、自社の専門性を活かせる内容にするのがおすすめです。また、情報を明確にする具体的な数字や根拠があると更に確率があがります。
AIの可読性を高める施策
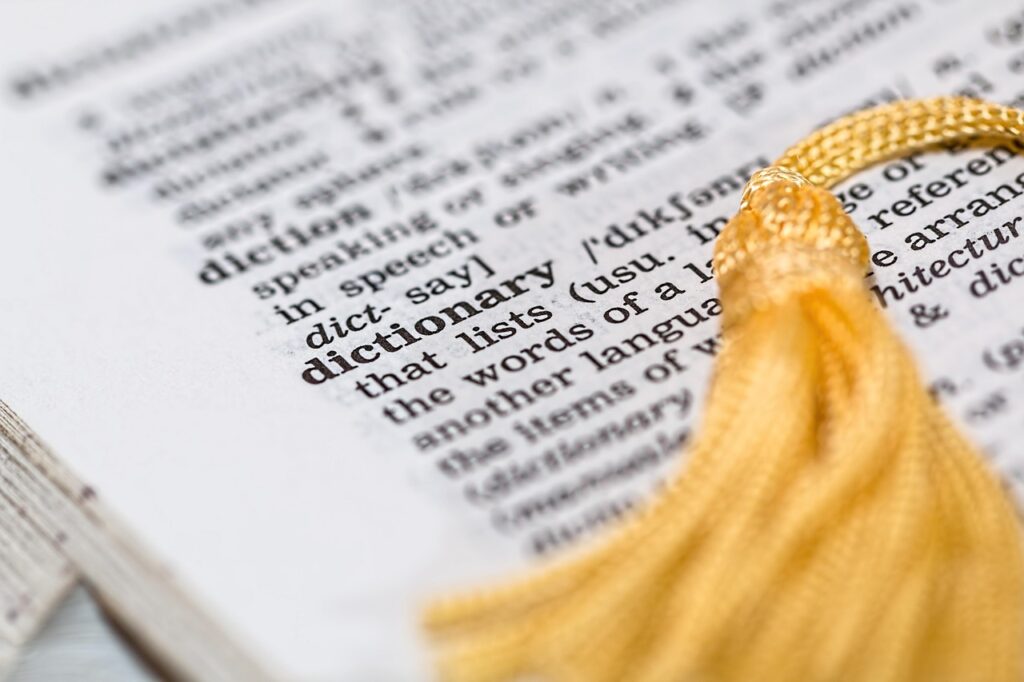
AIの引用・参照では「信用できて価値ある情報」が選ばれます。しかし、それもAIが情報を理解できていてこそです。そのため、AIにとっての可読性を高める施策は、自社コンテンツがAIに引用・参照される確率を最大化するという極めて重要な意味を持ちます。ここでは、AIの可読性を高める施策を解説します。
llms.txtの設置
「llms.txt」は、AIクローラーに対して自社サイトの情報構造や参照方針を明示する役割を持つテキストファイルです。AIクローラーにサイトの参照範囲や扱い方を指示し、情報収集の効率化をサポートする点で、SEOで活用される「robots.txt」とよく似ています。llms.txtが設置されることで、AIは自社サイトの内容を理解・要約しやすくなり、結果として引用精度を向上させます。この仕様は2024年9月3日にAnswer.AIの共同創設者であるジェレミー・ハワード氏が提案しました。
「llms.txt」は、AIクローラーへのアクセスルールを記載し、サイトのルートディレクトリ(例:https://example.com/llms.txt)に設置します。記載できるルールには、以下のような内容があります。
・参照の許可/拒否(Allow / Disallow)
AIにアクセスしてよい、あるいは禁止したいディレクトリやファイルパスを指定します。
・クロールの遅延/レート制限(Crawl-delay / X-Rate-Limit)
サーバーへの負荷を軽減するため、AIクローラーのアクセス間隔やリクエスト数を制限します。
・利用ポリシーの明示(X-Content-License / X-AI-Training-Policy)
コンテンツの著作権やAIによる学習利用の可否、ライセンス条件などを明示します。
・推奨コンテンツの指定(構造化データなど)
AIに優先的に参照・引用してほしいページやデータの場所をリスト化します。
・情報の鮮度(更新頻度)(Frequency)
コンテンツの更新頻度をAIに伝えることで、最新情報を優先的に参照させます。
「llms.txt」の設置は、AIクローラーに明確なルールを与えることで、情報の収集と利用を効率化し、生成AIが出力する内容の正確性・鮮度・信頼性を高めることができます。
構造化マークアップ
構造化マークアップとは、HTML内に「これは企業名」「これは製品名」などの意味情報(メタデータ)を付与することです。この処理を行うことで、検索エンジンやAIはページ内の情報を「文」ではなく「意味」として理解できます。たとえば、果物の「Apple」と企業の「Apple」は、文としては全く同じですが、構造化マークアップで「果物」や「企業名」といった属性を指定することで、AIは文脈を誤解せず正しく認識できます。
LLMOでは、構造化マークアップを通じて「記事(Article)」「よくある質問(FAQPage、Question、Answer)」「組織(Organization)」などの意味情報がよく付与されます。
| 意味情報 | 発信するシグナル | LLMOにおけるメリット |
| 記事(Article) | 情報の鮮度・権威性 | 誰が(author)、いつ(datePublished)、何を(headline)書いたかを明確にし、最新かつ質の高い情報であることを証明する。 |
| よくある質問(FAQPage) | 直接的な有用性 | 直接的な有用性ユーザーの質問に対する公式で権威のある回答を効率よく抽出しやすくし、AI検索の即答機能(スニペット)として採用されやすくする。 |
| 組織(Organization) | 情報源の信頼性 | その情報が誰の公式見解なのか、信頼できる企業が出しているのかをAIに伝え、情報の出典の明確化に役立つ。 |
引用・参照に関わるシグナルをマークアップで明確にすることで、AIが文脈を推測する手間を省きます。結果として、AIによる情報処理が円滑化し、引用や参照の精度が向上します。
記事構成と文章表現の最適化
AIは自然言語処理によって文章を解析するため、論理的な構成と一貫した文体が非常に重要です。 見出し・段落・箇条書きなどが整理されていれば、AIは文脈関係を把握しやすくなり、内容の主従関係を正確に捉えられます。また、専門用語の乱用や曖昧な表現を避けることで、AIが誤解なく意味を抽出できるようになります。
次項からは、AIから評価されやすい記事構成と文章表現を具体的に解説します。
AIから評価されやすい記事構成

AIから評価されやすい記事を構成するには、次の3つのポイントがあります。
・論理的に整理された構成
・見出しの「問いと答え」が明確
・テーマに必要な情報を網羅
ここでは、それぞれのポイントを解説します。
論理的に整理された構成
論理的に整理された構成は、情報の関連性や流れが明確なため、AIが内容を把握しやすくなります。AIは文章を「単語の並び」ではなく「意味の関係」として処理するため、段階的な展開や因果関係が整理されていることが重要です。逆に、脈絡のない文章は、AIにとってテーマの判定が難しく、参照・引用の確率が下がる傾向があります。論理的に整理された構成には次のような情報の流れがあります。
① ピラミッド構造(例:結論→理由→具体例)
人が情報を理解しやすい「抽象から具体の流れ」
② 時系列(例:過去→現在→未来)
人が経験や出来事を追体験しやすい「時間の流れ」
③ 順序(例:目的→準備→手順→完成)
人がタスクやプロセスを実行しやすい「段階的な流れ」
文章は人のための情報伝達手段です。人にとって論理的に理解しやすい構成こそが、AIにとっても正確な意味理解につながります。AIが文脈を正確に捉えるためにも、論理的な構成を常に意識しましょう。
セクションごとの「問いと答え」が明確
AIが効率的に情報を処理できるのは、ユーザーの疑問が明確で、何を知りたいのかがはっきりしている場合です。そのため、セクションごとの「問いと答え」が明確になっていると、AIはその情報を引用・参照しやすくなります。
「問いと答え」の構造を明確にする方法の一つは、見出し(H2〜H4)を直接「問い」として設定し、その直後の本文の冒頭で「答え」になる結論をすぐに提示することです。たとえば、次のような見出しと冒頭です。
見出し:食事制限なしで体重を落とすことは可能か?
冒頭:食事管理なしに体重を落とし、維持するのは極めて困難です。
見出し:ダイエット停滞期を乗り越えるには?
冒頭:食事内容や運動強度に変化を加えることが有効です。
見出しに「?」をつけて質問形式にし、冒頭でその質問の答えを提示しています。
このようなアプローチにより、AIはテキストの意図と内容の関係性を明確に理解できるようになり、より正確な情報処理が可能になります。
テーマに必要な情報を網羅
LLMは、文章単位ではなく記事全体の文脈を考慮します。つまり、部分的に正しい内容が含まれていても、全体としてテーマに必要な情報が欠けていれば、記事の専門性や信頼性を低く評価されかねません。AIから引用・参照されるには、網羅性も重要な要素です。
LLMO・SEOにおける「網羅性のある」とは、記事テーマとユーザーの検索意図に対して、必要な情報を過不足なく提供している状態を指します。そのため、網羅性を満たす記事を作るうえでは、「テーマの具体化」と「ターゲット設定」が欠かせません。
ありがちな失敗としては、網羅性を意識するあまり、読者層を考慮せずに情報を詰め込みすぎてしまうことです。たとえば、どんなジャンルでも、初心者向けと上級者向けの情報を混在させるのは避けるべきです。こうした記事は字義的に情報を網羅していても、初心者・上級者どちらの検索意図にも適合していません。テーマとターゲットを明確に絞り、必要な範囲を深く掘り下げて、網羅性を確保しましょう。
AIが理解しやすい文章表現
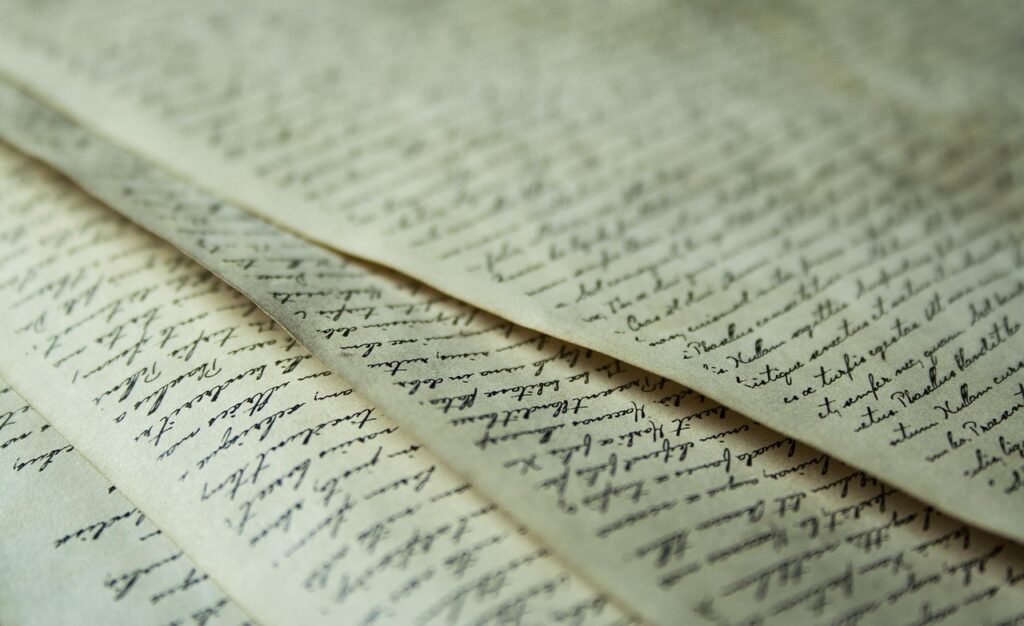
AIに評価されやすい構成のポイントが分かりました。では、LLMOでは、その構成でどのような文章を書けばいいのでしょうか? ここでは、AIが理解しやすい文章表現について解説します。
一文一義の原則
一文一義とは、「一つの文章に一つの情報だけを書く」という文章作成の原則です。文章を簡潔化し、読み手が誤解しない、理解しやすいように書くことを目的としています。この考え方はAIにも当てはまります。
AIは長く複雑な文章よりも、文ごとに一つの意味しか持たない構文を理解しやすい傾向にあります。 一文に複数の主張や説明が含まれると、AIが「どの情報が重要なのか」を正確に判断しづらくなります。
たとえば、「AI対策は重要であり、SEOにも効果があるため、早めに取り組むべきだ」という文には、3つの情報が含まれています。このような文章はAIにとって、何を主題とするかが判断しづらく、誤解を招きやすいといえます。
これを一文一義にすると、「AI対策は重要です」「AI対策はSEOにも効果があります」「AI対策は早めに取り組むべきです」となります。このように一文に一つの情報しか含まれないことで、AIは誤解せず文章を理解できるようになります。
ただし、これはあくまでAI視点のみで考えた場合です。すべての文章を一文一義で書いてしまうと、文章が冗長になり、人間視点で読みにくくなってしまいます。あくまで人間視点での読みやすさと両立する形で、一文一義を意識しましょう。
結論ファーストの構成
AIは、文脈を前から順に処理して意味を構築します。そのため、結論を冒頭に提示することで、AIが「何について説明しているのか」を早い段階で把握しやすくなります。逆に結論を後回しにすると、AIは途中の情報を補完しながら推測する必要があります。文脈の全体像が不明なまま各情報を処理するため、理解の正確性が下がってしまいます。
たとえば、「ダイエットを成功させるには、カロリー管理が必要です」という結論を冒頭で述べると、AIは以降の情報を「ダイエット成功にはカロリー管理が必要」という結論に基づいて推測します。逆に文末に置いてしまうと結論に基づいた情報判断ができないため、AIは途中の情報を暫定的な文脈で解釈します。これには、最終的に結論と情報を統合する際に誤った関連付けをしてしまうリスクがあります。
結論ファーストを徹底することで、「この情報は何のためにあるのか」を早い段階で明確にし、AIの理解を正確に導きましょう。
Q&A形式や箇条書きの活用
AIはQ&A形式や箇条書きを得意にしています。情報が明確に区切られるため、要素ごとの意味関係を解析しやすいからです。
たとえば、「ダイエットを成功させるには?」というテーマをQ&A形式にすると次のようになるでしょう。
Q(質問): ダイエットを成功させるのに必要なのは?
A(回答): 継続的なカロリー管理です。
このように、Q&A形式はユーザーの質問と回答が明確に分かれているため、意味関係をスムーズに理解できます。
また、箇条書きもAIにとって理解しやすい構成の一つです。たとえば「継続的なカロリー管理が必要な理由」を箇条書きにすると以下のようになるでしょう。
・摂取と消費のバランスを把握できるため、無理なく体重を調整できる
・食事内容の偏りに気づきやすくなり、健康的な食生活を維持できる
・一時的な減量ではなく、リバウンドを防ぐ長期的な習慣化につながる
複数の情報が独立した形で並ぶため、AIは項目間の関連や階層を明確に把握できます。Q&A形式や箇条書きで情報を構造化するのも、AIの文章理解を助けるポイントです。
まとめ
生成AIの普及により、情報収集の主流は検索から対話型AIへと移行しつつあります。従来のSEO対策だけでは、AI経由のユーザーを取りこぼしてしまうでしょう。
LLMOは、AIに自社コンテンツを正しく理解・参照してもらうための新しい対策です。SEOによる「検索での評価を高める施策」と、AIに伝わりやすい「構造的で簡潔な文章表現」を組み合わせることで、AI・検索エンジンの双方に評価されるコンテンツを作成します。
これからのWeb対策は「SEO」「 LLMO」の両方に対応する必要があります。Web集客力を維持するためにも、検索エンジンだけでなく、生成AIにも評価されるコンテンツを作成していきましょう。

