COLUMNコラム
【自社完結】インハウスSEOとは? 導入するメリット・デメリットなど基本知識を紹介
インハウスSEOとは、自社が外注に頼らず内製のSEO対策を実施することです。近年、SEOの重要性が広く認知されるようになり、「SEOを社内の担当者だけで運用したい」と考える企業が増えています。
確かに、外注に頼らずに自社でSEO対策を完結できれば、費用コスト削減やノウハウ蓄積など数々のメリットが期待できます。しかし、その一方で、自社でSEOを完結させようとすることで、多くの課題や必要業務が発生し、かえって非効率化するリスクもあります。
そこで、この記事ではインハウスSEOのメリットとデメリット、行うべき主要な業務など基本知識について解説します。インハウスSEOの導入に興味をお持ちの方は、ぜひこの記事をお役立てください。
インハウスSEOとは

インハウスSEOとは、社内主導でSEO対策を実施することです。「インハウス」とは「社内」を意味します。外注に頼らず自社でSEO対策を実施するため、意思決定のスピードや施策の柔軟性が高まるのが特徴です。
近年では企業のSEOに対する理解が深まり、SEOを自社内で完結させようとする動きが活発になっています。コスト削減やノウハウ蓄積を目的とした企業の間でインハウスSEOの注目が高まっています
インハウスSEOのメリット
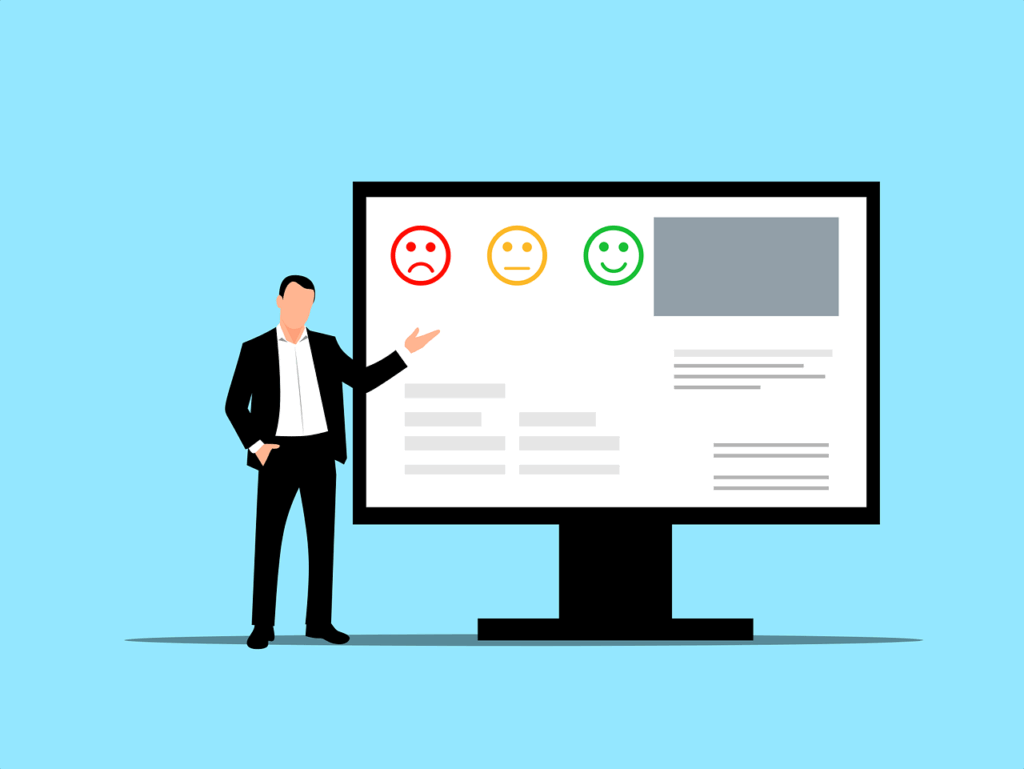
インハウスSEOを導入すると以下の効果が期待できます。
・SEOコンテンツの外注費を抑えられる
・自社内でPDCAを素早く回せる
・社内でSEOのノウハウを蓄積できる
・自社理解の高いコンテンツを制作できる
ここでは、インハウスSEOのメリットを4つ紹介します。
SEOコンテンツの外注費を抑えられる
SEOを外注する場合、記事作成や監修・修正など作業が発生するたびに費用コストがかかります。また、外注先との打ち合わせで発生する時間的なコストも小さくありません。このようなコストを、インハウスSEOなら内製化で削減することが可能です。
インハウスSEOの導入に成功すれば、限られた予算でより大きな集客や売上を狙える体制を構築できます。
自社内でPDCAを素早く回せる
PDCAとは、Plan(計画する)、Do(実行する)、Check(効果計測をする)、Action(改善策を実施する)の略語で、事業改善のサイクルです。
インハウスSEOでは、自社内で企画から実行・分析・改善までを一貫して管理できます。外注先が間に入らないので、分析結果をすぐに共有し、次のアクションを迅速に決めることが可能です。このような利点から、インハウスSEOではPDCAを素早く回せます。
PDCAのサイクルが早まれば、企業は市場変化に迅速な対応ができるようになります。また、効率的な学習を通じて、成長と目標達成を加速させる効果も期待できます。
社内でSEOのノウハウを蓄積できる
外注をメインにすると、SEOの知見が自社に残りにくくなります。一方でインハウスSEOを導入すれば、キーワード選定やコンテンツ設計、内部施策など主要業務を、自社担当者が経験できます。長く継続すれば、社内にSEOのノウハウを蓄積することが可能です。
SEOはWebマーケティングを行う上でほぼ必須です。他部署との連携や新規事業の立ち上げ時など活用の機会が多いスキルと言えます。ノウハウが蓄積されれば、将来的な外注費の抑制や、マーケティング力の強化につながります。
自社理解の高いコンテンツを制作できる
SEOを外注する際に、自社や業界への理解度を重視するクライアントは少なくありません。検索エンジンに評価されるには、ターゲット顧客の具体的なニーズやブランドイメージを正確に反映することも重要になるからです。
その点において、インハウスSEOは外注より圧倒的に有利です。「自社・業界に関する専門性の高さ」から、外注より高品質なコンテンツを作成できる土壌があります。業務に慣れさえすれば、外注よりSEOで高い成果を出せる可能性は十分にあります。
インハウスSEOのデメリット

メリットだけを並べると、インハウスSEOは魅力的な選択肢です。しかし、インハウスSEOの導入では、以下の課題と向き合うことになります。
- SEOの専門知識がある人材の採用・育成が必要になる
- すぐに効果が得られないので予算が承認されないことがある
- SEO対策が特定の担当者に依存するリスクがある
- 検索アルゴリズムの変化に対応しづらくなる
ここでは、インハウスSEOのデメリットを4つ解説します。
SEOの専門知識がある人材の採用・育成が必要になる
SEOはキーワード選定やコンテンツ設計、内部対策など多岐に渡るスキルが必要です。また、結果が出るまで時間がかかる施策なので、経験を積むのにも時間がかかります。インハウスSEOに必要だからと人材を採用・育成しようとしても、一朝一夕にはいかないのが現実です。
特に一から人材を育成する場合は、担当者の離職のリスクを避けるため、デジタル分野と相性のいい人材の選定から始める必要があります。
人材の採用・育成に時間がかかり、思うように成果を出せない可能性があるのが、インハウスSEOのデメリットです。
すぐに効果が得られないので予算が承認されないことがある
SEO対策は実施してから成果が出るまで早く3~6ヶ月、遅ければ1年以上かかるケースもあります。そのため、経営側にSEOの理解がないと、早々に見切りを付けられてしまって、予算が承認されないこともあります。継続的に投資を引き出してもらうためには、トラフィックやコンバージョン数など、分かりやすい成果のアピールが必要になるでしょう。
インハウスSEOは外注と比較してコスト削減が期待できますが、それはあくまで将来的な話です。
初期段階で経営側から見切りを付けられ、中途半端な内製化で終わってしまうリスクがあるのもデメリットです。
SEO対策が特定の担当者に依存するリスクがある
インハウスSEOでは特定の人にSEO業務を集中させがちです。そのため、会社のSEO対策が1人の担当者に依存してしまうリスクがあります。
たとえば、その担当者が退職や異動などでいなくなってしまうと、SEO施策の品質が落ちたり、進行が遅延したりするなどの事態が発生してしまう可能性があります。
ノウハウが会社にではなく、個人に蓄積されてしまうリスクがあるのも、インハウスSEOのデメリットです。
検索アルゴリズムの変化に対応しづらくなる
SEOの最新動向に敏感なのは、やはりSEOを本業とする外注です。インハウスSEOでは、内製化により検索アルゴリズムの変化に対応しづらくなるリスクがあります。
Google検索エンジンは常にアップデートを繰り返しています。アップデート後、コンテンツの評価基準が変化したことで、検索順位が変動してしまう事例は少なくありません。
このような変化が起こっても、SEO専門業者ならスムーズに対応できます。複数企業をモニタリングしているので、比較データを取りやすく、偏りのない分析ができるからです。一方で、基本的に自社データの分析しかできない自社SEOでは、どうしても対応が後手に回ります。
SEO専門業者に比べると検索アルゴリズムの変化に対応しづらいのも、インハウスSEOのデメリットです。
インハウスSEOに適性のある企業の特徴

インハウスSEOの導入にはメリットだけでなく、デメリットも少なくありません。そのため、事前に「自社がSEOの内製化に向いているか?」を確かめておくことも大切です。
インハウスSEOは、SEO専任者や社内理解の有無で難易度が大きく変わります。ここでは、SEOの内製化に適性のある企業の特徴について解説します。
社内にSEO専任者がいる
元から自社のホームページやブログページなどのSEO対策を行っている専任者がいれば、内製化もスムーズです。
専任者は日々の業務でSEOに関わっているので、インハウスSEOの導入時には、キーワード選定やコンテンツ、内部施策などを一貫してリードしてくれるでしょう。また、外注に比べて自社理解が深いため、他部署との連携や情報共有を通じて、顧客目線を反映した質の高い施策を打ち出せる素地があります。
最初から専任者がいる企業は、面倒な人材育成が必要なく、内製化が円滑に進みます。自社体制を迅速に構築できるため、インハウスSEOの導入に向いています。
社内でSEOの重要性を認識されている
社内でSEOの重要性が広く認知されているのも、インハウスSEOを成功させやすい企業の特徴です。
SEOは中長期的な視点で行う施策です。経営層に理解がないと初期段階で「効果なし」と断定され、内製化が頓挫してしまう可能性があります。また、社内での認識はインハウスSEOの強みを活かす上でも重要です。企業独自の視点でコンテンツを制作するには、他部署がSEOを理解し、積極的に必要な情報を共有してくれる体制が大切になります。
社内でSEOの重要性を認識されている企業は、SEO施策への投資や協力への理解があるため、インハウスSEOの導入に向いています。
インハウスSEOの導入手順

インハウスSEOはどのように導入するのでしょうか? 手順は大きく3つに分けられます。
①課題整理と目標設定
②社内体制の構築と必要人材の確保
③実行と改善を繰り返すPDCAサイクルへ
ここでは、順を追って解説します。
課題整理と目標設定
まずは、自社サイトの現状分析を行って課題を整理します。その上で、インハウスSEOで得たい成果や目標を設定します。
たとえば「コンテンツの独自が低い」「内製化で費用コストを削減したい」といった課題を洗い出したなら、「自社のノウハウをコンテンツに反映させて検索流入を増やす」「内製化で年間コストを30%削減する」など、具体的な目標を掲げます
課題と目標を明確にしたら、それを基に必要な人員やコストを検討します。
その際、インハウスSEO導入後の見込み成果を数値で提示できると、社内の理解を得やすいです。スムーズに内製化を進めるためにも、戦略設計の段階での提示を目指しましょう。
社内体制の構築と必要リソースの確保
戦略が決まったら、予算を調達し、社内体制を構築します。インハウスSEOでは、次のようなリソースが発生するでしょう
- コンテンツ作成に関わるWebライターや編集者などの人件費
- インハウスSEOの専任者にかかる人件費
- SEOの改善や分析に必要な有料ツールにかかる費用
この中で最も悩ましいのは、コンテンツ作成に関わるリソースです。SEOを達成させるには、ユーザーに求められる高品質なコンテンツの作成が前提になります。その上で、目標達成のために短期間で量産しなくてならないことも多く、リソースの確保が難しい場合もあります。
品質の維持が難しい場合は完全な内製化にこだわらず、一部業務を外部に委託する柔軟性も大切です。
実行と改善を繰り返すPDCAサイクルへ
社内体制を構築したら、実際にインハウスSEOを運用してみて、PDCAサイクルに乗せます。具体的には次の通りです。
施策を計画(Plan)
実際にコンテンツ制作や技術改善などを実行(Do)
順位変動や流入数、CVなどのデータを収集して評価(Check)
分析結果から改善点を特定し、次の施策計画に反映(Action)
このサイクルを短期に繰り返すことで、SEO施策の精度を高めていきます。検索エンジンの変化や競合の動きに対応するためにも、サイクルを継続していくことが大切です。
改善が行き詰まった場合は、SEOの内製化を支援している会社や専門家などのサポートを受けるのも選択肢の一つです。サポートを受けつつ人材育成をすれば、結果的にインハウスSEOの導入が早まります。
インハウスSEOで発生する主要業務

課題と目標を洗い出して戦略を立て、必要リソースを確保して社内体制を構築。その上で、PDCAサイクルを繰り返すのが、インハウスSEOの大まかな導入手順です。
インハウスSEOの理解を深めるには、実務レベルでどのような業務が発生するか把握しておくことも欠かせません。ここでは特に重要性が高い発生業務を7つ紹介します。
目標設定(KPI設定)
KPIとは、Key Performance Indicator(重要業績評価指標)の略です。インハウスSEOでは、最終目標を達成するための「中間目標の設定」と考えると分かりやすいでしょう。KPI設定は、リソース配分やPDCAサイクルの基盤になるので、インハウスSEOの導入で発生する業務の中でもとくに重要です。
たとえば「SEOの内製化で総費用コストを500万円削減したい」という最終目標に対し、KPIでは「コンテンツ制作の外注費を200万円削減」「リスティング広告費を150万円削減」といった数値化できる目標をできるだけ細かく、達成可能な範囲で設定していき、目標を具体化していきます。
このような具体的な目標は、成果を正しく評価し、施策の良し悪しを判断する上で欠かせません。リソースの浪費や期待値のズレといったリスクを軽減するためにも、最初にKPIを設定し、関係者間で共有することが非常に重要になります。
キーワード調査・選定
キーワード調査・選定は、コンテンツ施策の軸である「検索意図」を定める業務です。検索意図の特定は、ユーザーのニーズを理解し、それに応えるコンテンツを作成するのに不可欠です。適切にキーワード調査・選定が行われないと、SEO対策も的外れなものになってしまいます。
キーワードの調査・選定の手順は以下の通りです。
①SEO目的の明確化し、ターゲットユーザーを定める
②ターゲットユーザーの検索意図を考え、ニーズを予想する
③予想したニーズからキーワードを洗い出す
④キーワードをグルーピングして整理する
⑤キーワード候補を検索ボリュームや難易度などで評価し、優先順位をつける
⑥実際にキーワードでコンテンツを作成し、効果測定と改善を繰り返す
キーワード選定は、ユーザーが求める高品質なコンテンツを制作する基本で、検索順位や流入数の向上といった分かりやすい成果に直結します。逆に言えば、そこを怠るとユーザーが求めていないコンテンツを量産してしまうリスクがあります。成果を出して社内の信用を得るためにも、インハウスSEOではキーワード調査で狙うべきテーマを明確にすることが大切です。
コンテンツの企画・作成
キーワード調査は有効ですが、誰でもできて、似た答えに行き着くため、差別化がしにくいという欠点があります。そのため、高品質なコンテンツを作るには、検索エンジンに評価されるユーザーの問題解決や自社の独自性を盛り込むための企画も大切です。
たとえば、自社サイトを閲覧するターゲットユーザーを解析し、「ユーザーが抱える問題は何か」「その解決に役立つ情報は何か」などを整理します。ユーザーにとって有益なオリジナル情報を特定し、どう盛り込むかを考えるのが企画のポイントです。
企画が甘いと、ユーザーが本当に求めている情報とズレが生じたり、他サイトとの差別化が難しくなったりするリスクがあります。効率的に検索エンジンからの評価を高めるためにも、企画の手間を惜しまないようにしましょう。
SEOコンテンツのリライト
情報は、古くなるとユーザーのニーズを満たせなくなります。情報価値を維持するためにも、定期的なリライトは大切な業務です。
また、Googleの検索アルゴリズムは日々アップデートが繰り返されています。大規模なアップデートになると、これまで有効だったSEO対策が無効化され、検索順位が変動することも珍しくありません。コンテンツを新しい評価基準に対応させるためにも、リライトは必須になります。
近年ではコンテンツ作成にAIを活用する機会が増えました。Googleは「AI利用コンテンツでもユーザーが求める品質が維持されているなら評価する」としつつも、AIによる低品質コンテンツの大量生産には監視の目を強めています。実際に2024年3月のGoogleコアアップデートでは、AIによるテンプレ大量記事を含む、低品質サイトが軒並み順位を下げています。
リライトを怠ると、情報が古くなって利便性を提供できなくない、アルゴリズムの変化に対応できず検索順位を落とす、などのリスクがあります。公開後の定期的なリライトも重要業務です。
内部対策
検索エンジンがコンテンツを適切に理解するのを補助する内部対策も、インハウスSEOで発生する重要な業務です。内部対策が不十分だと、検索エンジンにコンテンツの価値を伝えられません。SEOの土台を整えるためにも、検索エンジンに配慮した技術的な対策が必要になります。
内部対策は主に、クローリングの最適化とインデックスの最適化の2つに分類できます。
クローリングは、検索エンジンのロボットであるクローラーがWebサイト上のリンクを辿り、ページから情報を自動収集するプロセスです。
具体的な対策としては、クローラーにサイト構造を伝えるXMLサイトマップの作成・送信や、読み込まなくてもいいページを指定するrobots.txtファイルの作成などがあります。
インデックスは、クローラーが収集した情報を検索エンジンのデータベースに保存し、検索結果に表示できるように整理するプロセスです。
具体的な対策としては、情報構造を示すタイトルタグや見出しタグの最適化、検索結果で適
詳細な要約を表示するメタディスクリプションの作成などがあります。
内部対策をしないと、ページが正しくクロール・インデックスされず、順位が上がりにくくなります。質の高いコンテンツを制作しても正当に評価されず、SEO効果が得られません。ユーザーだけでなく、検索エンジンにとっての「分かりやすさ」にも配慮しましょう。
サイト改善
Webサイトを改善し、ユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させることも、インハウスSEOで重要になる業務です。UXとは、製品やサービスの使用体験のことです。Webサイトでは「使いやすさ」「快適さ」などが当てはまります。
具体的な対策としては、「使いやすさ」なら、近年のユーザーの利用スタイルに合わせて、Webサイトをスマホ対応のモバイルフレンドリーにするなどが挙げられます。また「快適さ」なら、ページの表示速度や視覚的安定性を上げるために、コアウェブバイタルを改善するなどがあるでしょう。
コンテンツの品質が高くても、サイト自体が使いにくいとユーザーが離脱しやすくなります。SEOを達成するには、継続的なサイト改善も大切です。
SEO効果の測定
SEO対策を成功させるには、対策結果を評価し、課題を見つけて改善していくプロセスが欠かせません。ここで必須になるのがSEO効果を数値として計測する業務です。SEO効果を数値として計測できる指標は主に以下の3つです。
- 検索順位
- 自然検索での流入数
- 自然検索でのコンバージョン数
これらの指標はGoogle AnalyticsやSearch Consoleなどのツールでモニタリングできます。数値が出たら、目標値(KPI)と照らし合わせて、どの施策が効果的だったか分析します。
SEO効果を計測できないと、どの施策が有効だったか判断できず、対応が場当たり的になりがちです。PDCAを回すためにも、必ず効果測定を実施しましょう。
インハウスSEOを成功させるコツ
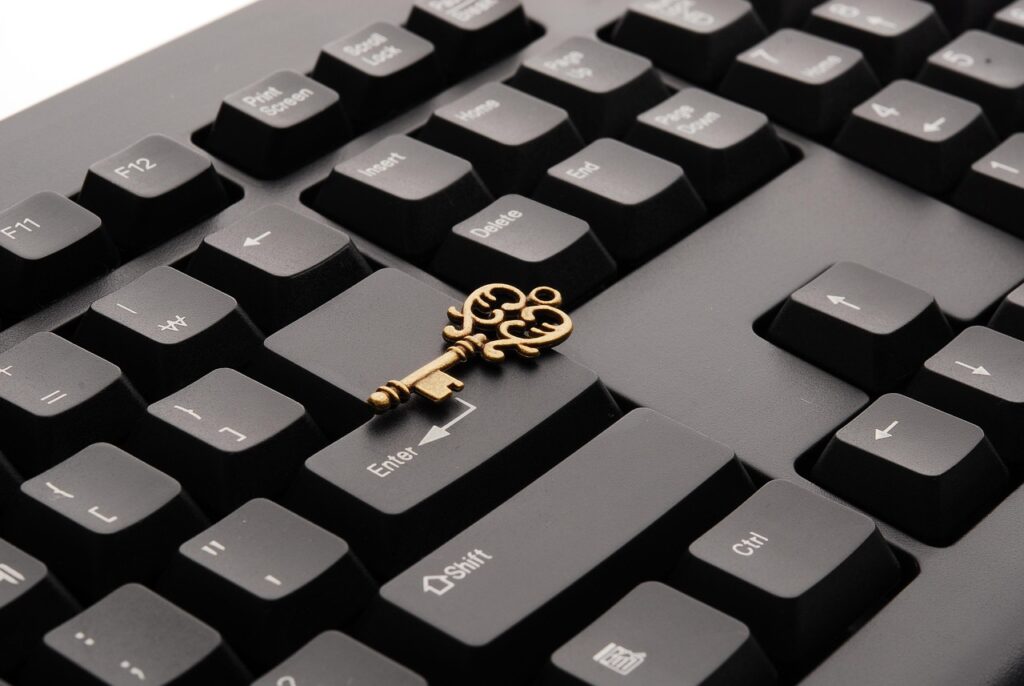
SEOの内製化は魅力的です。しかし、デメリットも多く、専門知識を必要とする様々な業務が発生するため、成功させるのは容易ではありません。
インハウスSEOを成功させるにはどうしたらいいでしょうか? 最後にインハウスSEOを成功させるコツを4つ紹介します。
社内でSEOの重要性を共有する
1つ目は、社内全体でSEOの重要性を共有して、他部署との協力関係が築きやすい環境を作ることです。
周囲の理解と合意があることで、施策の実行がスムーズになり、長期的に安定して成果を出せます。また、ノウハウが全体で共有されることで、SEOが担当者に依存するリスクも軽減できるでしょう。
協力を求めたい他部署や社員がSEOの価値を理解していないと、施策が後回しになったり、適切な対応が得られなかったりします。ビジネス上の成果を共有することで、全員が同じ目標を持てるようにすることがポイントです。部署の壁を越えた協力体制が、インハウスSEO実現のカギになります。
専任のSEO担当者を確保する
2つ目は、内製化の要になるSEOの専任者を事前に確保することです。
SEOは専門性が高いだけでなく、継続的な分析や改善が必要な業務です。専任者を決めてこそ、サイト全体のSEO戦略を一貫して進められます。社内にSEO経験者がいない場合は、外部からの採用も検討しましょう。
SEOを兼任業務にすると他業務に追われて、内製化の難易度が上がります。担当者が施策を計画的に進められる体制を築くことが大切です。専任者を事前に確保しておくのが、インハウスSEO実現のカギになります。
外注を活用して段階的に内製化する
3つ目は、最初は自社と外注で役割分担をして段階的に内製化していくことです。
SEO業務は多岐に渡り、習熟にも時間がかかります。一度にすべてを内製化しようとすると、リソース不足に陥って、破綻してしまうリスクがあります。最初は自社と外注で業務範囲と役割を明確にし、徐々に内製化を進めていくのがおすすめです。
たとえば、最初はコンテンツ制作に関わるキーワード選定や記事作成などの業務だけを自社で担当し、内部対策やサイト改善などテクニカルな業務は外注に任せる、といったようにです。この場合、SEO担当者が外注から仕事を見て学んだり、定期的にアドバイスをもらったりしながら、自社の業務範囲を少しずつ広げていきます。役割分担を明確にして無理なく内製化を進めていくことが、インハウスSEOの実現につながります。
インハウスSEO支援会社を活用して担当者を育成する
4つ目は、インハウスSEO支援会社を活用して、定期的に担当者のSEO知識を強化・アップデートしていくことです。
SEOスキルを持つ担当者でも、内製化で自社のサイトデータだけを見ていると情報や知識がズレていきます。担当者の育成やリスク回避の意味でも、支援会社を活用して定期的にSEOの最新情報や専門知識を学習するのは有効な手法です。
SEOはGoogleのアップデートで内容が変化し続ける分野です。独学で進めると、時間がかかるだけでなく、古い情報を元に誤った方向で対策を進めてしまうリスクがあります。信頼できる支援会社を活用して着実にSEO担当者を育成するのも、インハウスSEOを成功させるポイントです。
まとめ
インハウスSEOを成功させるには、良い部分だけを見るのではなく、デメリットや内製化で発生する業務を把握し、事前に対策を講じておくことが大切です。
SEO業務は人的・学習コストが多くかかります。行き当たりばったりに内製化を進めるとリソース不足に陥り、破綻してしまうため慎重に行う必要があります。事前に必要人材や社内理解を得てから、徐々に内製化を進めていくのがポイントです。
インハウスSEOの導入を検討している方は、デメリットや内製化で発生する業務を把握し、万全の準備を整えることを心がけましょう。

